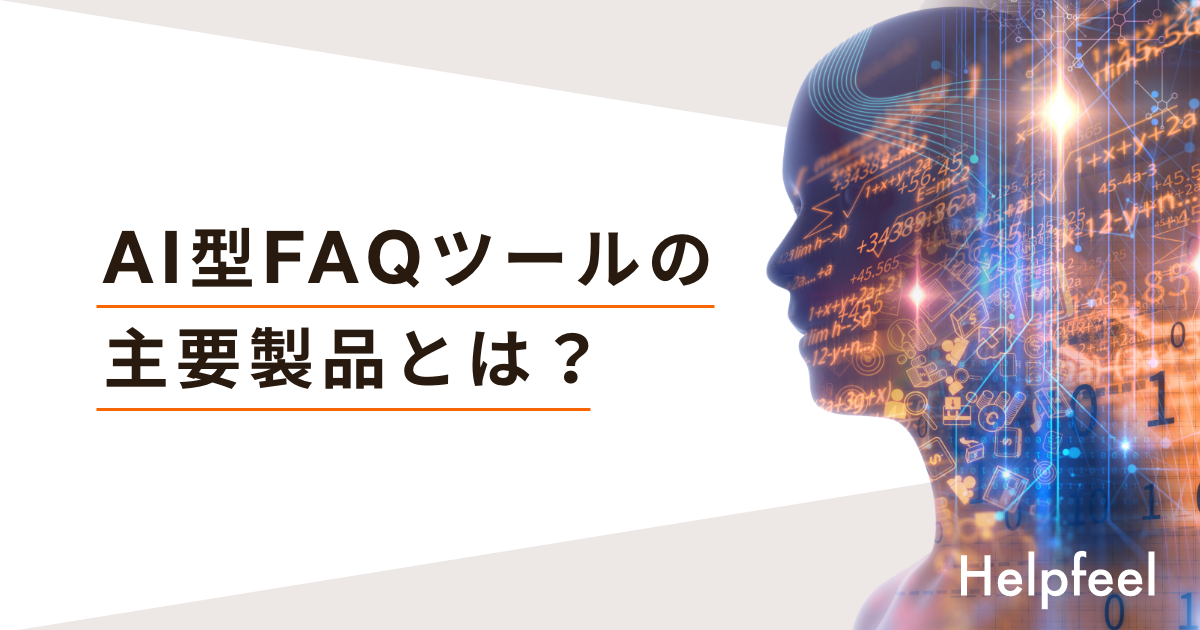コールセンターのCPHとは生産性の指標のひとつ
CPHとはCall Per Hour(コール・パー・アワー)の略称で、生産性を測る指標のことです。コールセンターにおいて、オペレーター1人が1時間あたりに応対した電話の本数(コール数)を指しています。
CPHに含まれる内容は、具体的には下記のとおりです。
<コールセンターのCPHに含まれる内容>
- ユーザーからかかってくる電話への応対
- ユーザーの電話応対後の事務作業
CPHは、個々のオペレーターやコールセンター全体におけるKPIのひとつです。この数値が高ければ高いほど、高いスキルを持つオペレーターが迅速に電話応対している、またはコールセンターとして効率的な運用が実現できているといえます。
一方で、CPHを過剰に追い求めた結果、1件あたりの電話応対時間が短くなりすぎるといった理由で、顧客満足度が低下する可能性もあります。応対品質と効率化のバランスをとるのが、CPH管理の重要なポイントといえるでしょう。
コールセンターのCPHの計算方法
コールセンターのCPHは、下記の計算式で算出します。
<コールセンターにおけるCPHの計算式>
CPH=オペレーターの総電話応対件数÷総稼働時間
個人のCPHは、コールセンターにおいてオペレーター1人が電話応対したすべての件数について、総稼働時間で割るという計算によって求められます。仮に、オペレーター1人が6時間稼働して54件の電話応対を行った場合は「54÷6=9」となり、1時間あたりのCPHは9(件)となるのです。
コールセンター全体のCPHを計算する場合は、全体の数値を用いましょう。
例えば、オペレーター20人が4時間ずつ稼働して、全員で1,000件の電話応対を行ったとします。この場合の計算式は「1,000÷20÷4=12.5」となり、コールセンター全体の1時間あたりのCPHは12.5(件)となるのです。
コールセンターのCPH以外のKPI
コールセンターにおけるKPIは、CPHだけではありません。ここでは、コールセンターにおけるCPH以外のKPIについて解説します。
ATT
ATT(Average Talk Time)とは、オペレーター1人が1件あたりの電話応対でかかった「平均通話時間」のことです。具体的には、オペレーターがユーザーの電話を受けてから切るまでの時間を指しています。
ATTの計算式は、下記のとおりです。
<コールセンターにおけるATTの計算式>
ATT=総通話時間÷総応対件数
ATTが長いほど、オペレーターがユーザーとの通話を終えるのに時間がかかっており、生産性が低い業務を行っている可能性があるので注意してください。
ATTを短縮するには、迅速かつ正確な電話応対ができるように、オペレーター応対マニュアル(トークスクリプト)の作成などを行う必要があるでしょう。
ACW
ACW(After Call Work)も、コールセンターにおけるKPIのひとつです。ACWは「平均後処理時間」という意味で、具体的にはオペレーター1人がユーザーの電話応対後に、通話内容や伝達事項の入力といった事務処理を行う際の作業時間のことを指します。
ACWの計算式は、下記のとおりです。
<コールセンターにおけるACWの計算式>
ACW=電話応対後の事務作業にかかった時間÷電話応対件数
ACWが長い原因として、オペレーターの教育不足や、電話応対後の事務作業が煩雑である可能性が考えられます。
AHT
AHT(Average Handling Time)とは、オペレーター1人による1件あたりの「平均処理時間」のことです。この平均作業時間は、電話を受けてから、電話応対後の事務作業が完了するまでを指しています。
AHTの計算式は、下記のとおりです。
<コールセンターにおけるAHTの計算式>
AHT=ATT(平均通話時間)+ACW(平均後処理時間)
AHTの短縮によって、コールセンター全体の生産性向上やコストの削減につながります。しかし、応対品質の低下や、それに伴う顧客満足度の低下には注意が必要といえます。
稼働率
コールセンターにおける稼働率とは、オペレーターの出勤から退勤までの勤務時間のうち、電話応対に費やしている稼働時間がどれぐらいなのかを表したKPIです。稼働率は、下記の計算式で導き出すことができます。
<コールセンターにおける稼働率の計算式>
稼働率=(電話応対時間+電話応対後の事務作業時間+待機時間+保留時間)÷(勤務時間-休憩などによる離席時間)×100
コールセンターの稼働率は、低すぎると人余りを起こしているといえます。ただ、高ければいいというわけではなく、80~85%を保っているのが適正といえるでしょう。
稼働率が85%を超えると、オペレーターが常に電話応対している状況に近く、ストレスや疲労により生産性低下を招きやすくなります。場合によっては離職率が高まる可能性があるので、コールセンターの稼働率管理には注意が必要です。
コールセンターでCPHを活用する際の注意点
コールセンターのCPH活用においては、いくつか気をつけたい点があります。ここでは、CPHの活用における注意点について解説します。
CPHの数値だけを見て判断しない
CPHの数値だけを見て、個々のオペレーターやコールセンターの生産性を判断しないように注意してください。コールセンターの生産性は、各種KPIも同時にチェックする必要があります。
具体的には、CPHを向上させようとして、オペレーターに対し、行きすぎた目標設定をした場合があります。オペレーターが通話時間をとにかく短くしようとしてATTが低下する一方で、ユーザーが「応対が不十分、不親切」という印象を抱き、結果として顧客満足度に大きな影響が生じる可能性があるのです。
また、オペレーターの人数を増やして総電話応対件数が増えたものの、電話応対後の事務作業フローやシステムに問題がある場合、CPHはなかなか改善しないでしょう。この場合は、ACWも併せてチェックし、対策を講じる必要があります。
CPHが低下した場合は、原因を必ず分析する
コールセンターにおいて、CPHの数値が過去と比較して低下した場合、原因の分析が必要不可欠です。
CPHの低下は、具体的には下記の原因が考えられます。
<CPHが低下する主な原因>
- オペレーターのスキル不足
- オペレーターの人数が不十分
- 応対時間や保留時間が長い
- 応対マニュアルが未整備
- 電話応対後の入力用システムが煩雑
CPHの低下は、オペレーター起因だったり、応対マニュアルや入力システムなどコールセンターの職場環境起因だったりします。
場合によってはこれらが複合的に組み合わさっている可能性もあるため、丁寧な分析をした上で、適切な対応策を講じましょう。
CPHを無闇に下げようとしない
コールセンターのCPHの数値を問題視し、無闇に下げようとしたりする行為には注意が必要です。製品・サービスやコールセンターの職場環境など、さまざまな要因で目標値は変わるからです。
また、顧客満足度や効率性のどちらを重視するかによっても、目指す数値は変わります。
一般的に、生産性の指標であるCPHは、電話応対件数を増やしたり、稼働時間を短くしたりすることで向上します。ただし、「CPHが高いから良く、低いから悪い」とは、一概に判断できない面があります。
具体例として、製品・サービスが複雑な構造だったり、顧客満足度を考えて丁寧な電話応対を求められたりする場合、CPHはどうしても低くなります。一方で、簡単な説明のみで電話応対が完了できる場合、CPHは高くなる傾向があるのです。
企業の方針や製品・サービス、またはオペレーターなどに応じて適切なCPHを目標値として設定し、活用する必要があるといえるでしょう。
コールセンターにおけるCPH改善のためのポイント
コールセンターにおいて、CPH改善を行う場合にはいくつか押さえておきたいポイントがあります。コールセンターにおけるCPH改善のためのポイントは、下記のとおりです。
FAQの改善・充実
コールセンターのCPHを改善するポイントのひとつとして、FAQの改善・充実が挙げられます。
FAQとは、ユーザーから頻繁に来る質問と、それに対する回答がまとめられたページのことです。ユーザー向けのFAQを改善・充実させることで、ユーザーの自己解決を促し、解決率を高めます。結果として、オペレーターの負担軽減と生産性向上が実現するでしょう。
また、オペレーター向けに作られた社内用のFAQの内容や機能を充実させる方法も、CPH改善手段のひとつです。
電話応対するオペレーターは、FAQ内を検索・参照することで回答の質を平準化できるほか、回答に要する時間を短縮できるはずです。検索性の高いFAQであれば、さらに効果的といえます。
応対マニュアルの整備
応対マニュアルの整備も、CPH改善に大きく貢献するポイントです。
コールセンターにおける応対マニュアルは、トークスクリプトとも呼ばれる電話応対用の台本です。電話応対時のやりとりの流れがある程度定型化されているため、経験が少ないオペレーターでも過不足のない電話応対が可能となります。
経験豊富なオペレーターの応対を参考にして作り込まれた応対マニュアルによって、CPHやATTを短縮することができるでしょう。
オペレーターの教育・研修
経験が乏しいオペレーターの教育を行ったり、研修制度を充実させたりすることも、CPH改善のための効果的なポイントといえます。
ばらつきのあるオペレーターのスキルを一定の水準にそろえることにより、コールセンター全体のCPHを改善させ、生産性を高めることができるでしょう。
ただし、教育・研修制度の充実でオペレーターのスキルアップに取り組む場合には、ある程度の期間や高い教育コストを要する場合があるので、導入時には注意が必要です。
システム面の改善
コールセンターのCPH改善には、電話応対後の事務作業に関する工程の見直しも大事なポイントです。
電話応対の内容を入力したり、申し送りしたりするシステムを改善することに伴って、オペレーターのACWやCPHは改善されるでしょう。
具体的な仕組みとしては、AIを活用した自動入力システムや応対の要約自動生成システムなどを導入することが挙げられます。これらのシステムにより、オペレーター間の入力速度や正確性の差が生まれにくくなり、コールセンター全体の生産性向上にもつながる可能性が高まります。
コールセンターのCPH改善のため、FAQシステムを活用しよう
コールセンターにおいてCPHは、個々のオペレーターやコールセンター全体の生産性を測る指標のひとつです。ただし、無闇にCPHを下げようとすると負担が生じ、オペレーターの生産性低下や早期離職につながる可能性も考えられます。
コールセンターにおいてCPHを改善する方法として、AIを活用したFAQシステムやチャットボットの導入が効果的です。
AIの適切な活用によって、オペレーターの負担を減らして生産性を高めるだけでなく、ユーザーの利便性向上も期待できるというメリットがあります。自社のコールセンターの課題を把握して、適切な対策を講じましょう。
例えば、AIを活用した検索型FAQシステム「Helpfeel」は、生成AIと独自技術でユーザーの検索意図をくみ取り、必ず欲しい回答に導きます。これによってユーザーの自己解決を促し、問い合わせ数を64%も削減した実績があります。
コールセンターの生産性向上やユーザーの利便性向上を目指している方は、「Helpfeel」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。