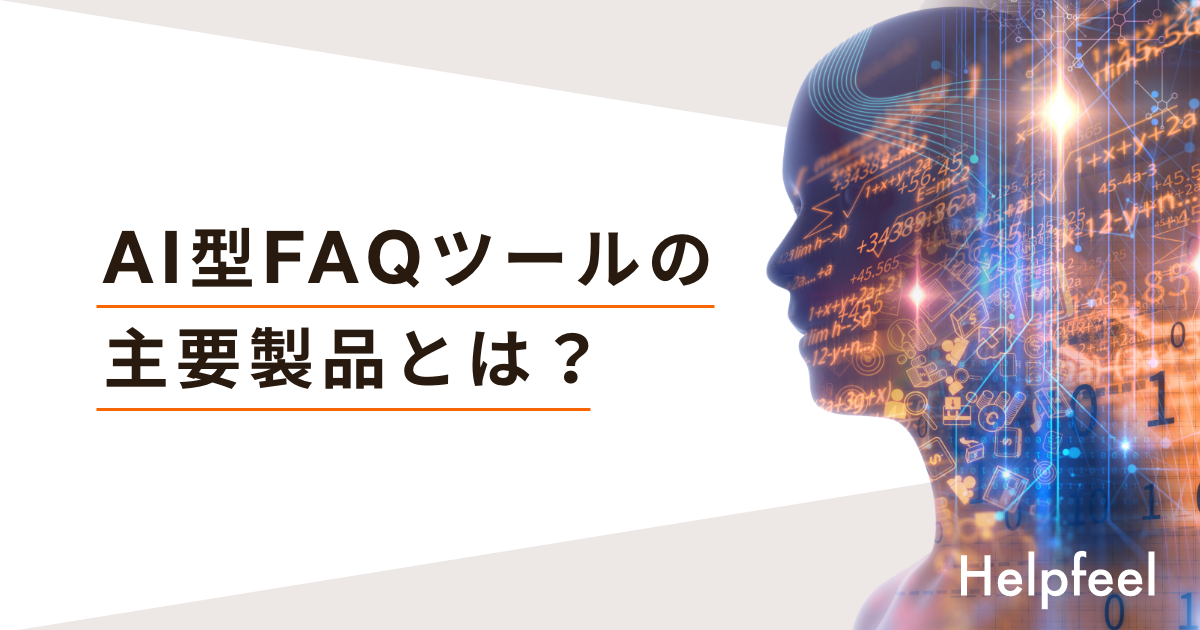ヘルプデスクの主な役割とは

ヘルプデスクとは、製品の使用方法や注文方法などの基本的な質問の回答から、トラブル対応や高度な内容のサポート、クレーム対応まで、さまざまな質問や相談に幅広く対応する部署です。問い合わせ手段は、電話やメール、チャットが主流になっています。
ヘルプデスクに似た職種として、テクニカルサポートやカスタマーセンター、コールセンターなどが挙げられます。企業によって多少の違いはありますが、以下のような役割を果たしていることが多いです。
- テクニカルサポート:より高度な技術的知識を必要とする問い合わせに対応
- カスタマーセンター:顧客対応に特化し、製品やサービスを購入する前後の顧客からの問い合わせに対応
- コールセンター:電話対応がメイン。問い合わせ対応だけでなく、電話での営業活動などを行う場合もある
ヘルプデスクの主な役割は以下の3つです。
1. 対象の製品・サービスに関する問題解決のサポート
ヘルプデスクでは、対象の製品やサービスに対する疑問や質問、トラブルの連絡を受け、顧客が問題解決できるようサポートしています。例えば、顧客が購入した自社製品の使い方の紹介や故障時の対応受付などが該当します。
トラブルが発生した際は、一次対応として技術的な支援も実施します。ヘルプデスクが迅速に対応することで早期に問題が解決され、問い合わせした側の生産性を高めることも可能です。
2. 顧客満足度の向上
ヘルプデスクは製品やサービスを購入した顧客と多くの接点を持つ部署です。そのため、ヘルプデスクは顧客満足度を向上させる役割を果たしています。ヘルプデスクが専門知識を持って速く正確に対応し、顧客の根本的な問題まで解決すれば、顧客満足度の向上につながる可能性が高まるでしょう。
3. ナレッジの蓄積と製品・サービスの改善
ヘルプデスクには顧客からあらゆる質問やトラブルが集まります。こうした質問やトラブルの内容、対応方法などは、製品やサービスに関するナレッジやノウハウとして蓄積することも可能です。特に、過去のトラブルとその対処法の記録は、クレームの再発防止や新人教育にも役立ちます。
また、顧客の声を集計して開発部署にフィードバックすれば、製品やサービス自体の改善につなげられるほか、社内のヘルプデスクなら、社内システムの運用のあり方を見直すこともできるでしょう。
ヘルプデスクの種類と主な業務内容

さまざまな役割を果たすヘルプデスクには、大きく分けて2つの種類があります。それぞれの業務内容について解説しましょう。
社外ヘルプデスク(顧客向けヘルプデスク)
社外ヘルプデスクは、顧客や社外の関係各社などからの問い合わせに対応する部署です。自社の製品・サービスの使い方や使用中のトラブル、クレームなどを受け付け、社内の関連部署と連携しながら顧客の問題解決に取り組みます。
電話やメール・チャットを用いて遠隔で対応することを基本としていますが、必要に応じて顧客訪問や短期間の常駐を実施することもあります。
社内ヘルプデスク(従業員向けヘルプデスク)
社内ヘルプデスクは、社内のIT部門の中に設置されることが多い部署で、従業員からの質問やトラブルに対応しています。例を挙げるなら、社内で使用しているPC機器やネットワーク、業務アプリなどに関する問い合わせやトラブル対応などです。
これに加え、IT関連のマニュアルを作成したり、新システムを導入する際に使い方やルールに関する勉強会を開催したりと、さまざまな業務を行っています。
ヘルプデスク運用の「よくある課題」

すでに社内外に対するヘルプデスクを持っている企業では、どのような課題を抱えているのでしょうか。よく耳にする課題について紹介します。
ヘルプデスク担当者の業務負荷が大きく、モチベーションを維持しにくい
ヘルプデスク特有の課題として多いのは、事業が好調で顧客数が増えている時ほど、ヘルプデスクへの問い合わせが増え、業務がひっ迫しやすくなることです。嬉しい悲鳴とも言えますが、多忙な状態が続くと、ヘルプデスク担当者のモチベーションが維持しにくくなります。
また、ヘルプデスクにはさまざまな質問や疑問が寄せられるものの、中には「よく聞かれる質問」があります。同じような質問ばかり寄せられると担当者の徒労感が強くなってしまうでしょう。
加えて、ヘルプデスクでは突発的なトラブルの連絡も多く、対応者はいつどのような問い合わせが来るかを予測できません。そのため、トラブルの同時多発や、終業間際の複雑な問い合わせによって、思わぬ残業が発生することもあります。こうした業務計画の立てにくさや、臨機応変な対応が求められることも、担当者の業務負荷を重くしています。
業務が属人化しやすい
ヘルプデスクには、より専門性の高い回答や技術的な対応が求められる問い合わせも寄せられます。こうした問い合わせに対して、ヘルプデスク経験が長い従業員や、技術的な知識レベルの高い従業員ばかりが対応していると、次第に業務が属人化し、対応できる人が限られてしまいます。
業務が属人化すると、対応できる従業員が不在の際の業務効率が落ち、顧客満足度の低下を招く恐れがあります。また、人を増やしてもなかなか新人が育たず、組織としての生産性が低下することも懸念されるでしょう。
対応品質を向上させる方法がわからない
ヘルプデスクの対応品質にはさまざまな指標がありますが、選択すべき指標や改善方法がわからず、行き詰まるケースも見聞きします。
例えば、CPH(対応件数)、ATT(平均通話時間)、ACW(対応後の作業時間)などに表れる「対応の速さ」を高めるのか、クレーム率、一次解決率といった「対応の質の向上」に取り組むのかを決められない、といった場合があります。
こうした課題をそのままにしておくと、結果としてヘルプデスクの対応力向上への取り組みが遅れてしまうでしょう。
過去の問い合わせ内容をうまく活用できていない
ヘルプデスクの担当者から「日々の対応に追われて、問い合わせの記録を残せていない」という声も聞きます。過去の問い合わせ内容を活用できていないと、顧客からの同じ質問に対して違う回答をしたり、担当者が変わる度に顧客が一から質問内容を伝える手間が生まれたりと、顧客対応の品質が低下しやすくなります。
また、日々の業務量が重すぎるために、業務改善に取り組めないもどかしさを感じているヘルプデスクも見受けられます。
ITの知識・スキルのキャッチアップが追いつかない
IT技術は日々進化し、さまざまなソフトウェアやOS、ウイルス対策ソフトなどがリリース、アップデートされています。特定のOSがバージョンアップされて仕様が変わると、自社の製品・サービスに不具合が出ることもあり、対策が必要です。
特に社外向けのヘルプデスクでは、顧客の使用環境にばらつきがあるため、幅広いOSやソフトウェアの最新情報を知っていることが求められます。しかし、日々の業務で忙しいと学びの時間が確保できず、問い合わせを受けてから最新情報を調べるため、業務が停滞しがちです。
ヘルプデスク運用を改善・効率化する方法

ヘルプデスクの運営上の課題を克服し、品質を高めるためには何ができるでしょうか。ここからは、ヘルプデスクの運用を改善する方法を解説します。
公式サイトの「よくある質問(FAQ)」や社内マニュアルを改善する
最初に取り組むべきことは、公開している情報の質を向上させることです。社外ヘルプデスクなら、自社サイトにある「よくある質問」の内容を見直し、顧客に必要な情報を簡潔に伝えられるよう修正します。社内ヘルプデスクなら、社内マニュアルなどに掲載している情報を見直しましょう。
たびたび寄せられる質問の回答や、トラブルの対応方法を広く共有することで、顧客や従業員の自己解決を促し、同じような問い合わせを減らすことができます。
▼FAQについては別の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
ITツールを導入して業務効率化を図る
近年はIT技術の進化により、ヘルプデスクで活用できるツールが多く生まれています。FAQシステムを導入してFAQページ内の検索性を高めたり、問い合わせフォームを導入してメインの対応方法を電話からメールに変えたりして、業務効率化を図ることが可能です。
メールやチャットの自動応答機能を使えば、人の手を介さずに定型的な質問に回答できます。また、ツールの導入は業務効率化だけでなく、対応品質の底上げにもつながります。こうしたITツールを効果的に活用するとよいでしょう。
ナレッジを収集し、担当者のスキルを向上させる
社内にあるナレッジを集めて共有すると、担当者のスキル向上や業務の属人化解消ができます。収集しやすいナレッジの例は、以下のとおりです。
- 過去の問い合わせ事例
- 「よくある質問」の回答集
- 顧客対応に関する基本的なポイント
- 最新のIT技術や業界の動向
さらに、こうしたナレッジをヘルプデスク以外の部門にも公開することも効果的です。定期的な社内研修や勉強会を開催してナレッジを共有したり、ロールプレイングによってスキルを高めたりすると、担当者や組織全体のアップデートにつながります。
ヘルプデスクの効率化に活かせるITツール

これからヘルプデスクの運用改善を具体的に検討するなら、以下のようなITツールが役立ちます。効果的な使い方も解説しましょう。
FAQシステム
FAQシステムとは「よくある質問(FAQ)」とその回答を作成・掲載をサポートするツールのことです。
網羅的なFAQを作成しFAQ内の検索性を高めると、顧客が自分で疑問を解決できるようになります。似たような問い合わせが集中することも防げるでしょう。
FAQシステムを導入することで、ヘルプデスクへの問い合わせが減少すれば、ヘルプデスク担当者は難易度の高い質問やトラブル、クレームに集中して対応できるようになります。
▼FAQシステムに関するお役立ち資料もご用意していますので、ぜひ併せてご覧ください。

チャットボット
チャットボットとは、AIなどが顧客からの質問に自動で返答するプログラムのことです。寄せられた質問に対してチャットボットが自動でメッセージを返信するため、24時間365日、即時対応が可能になります。また、会話形式で対応するため、人と会話をしながら疑問を解決できるような手軽さも魅力です。
▼なお、チャットボットを使った業務改善については、こちらで解説しています。合わせてご覧ください。
ナレッジ共有ツール
ナレッジ共有ツールとは、業務や製品、サービスに関する情報を蓄積・共有できるツールのことで、特に社内ヘルプデスクでよく活用されています。
ナレッジ共有ツールには、テキストで情報を集約する「社内Wiki」や動画・画像も蓄積できるツールなど、さまざまな種類があります。FAQシステムを社内のナレッジ共有・検索ツールとして利用することも可能です。自社に合ったツールを探してみるとよいでしょう。
FAQシステムによるヘルプデスク運用改善の事例

業務改善に役立つITツールのうち、社内・社外両方のヘルプデスクで有用性が高いものが、FAQシステムです。そこで、FAQシステムを活用してヘルプデスク業務を改善した事例を2つ紹介します。
▼本記事に関連したお役立ち資料もご用意していますので、ぜひ併せてご覧ください。
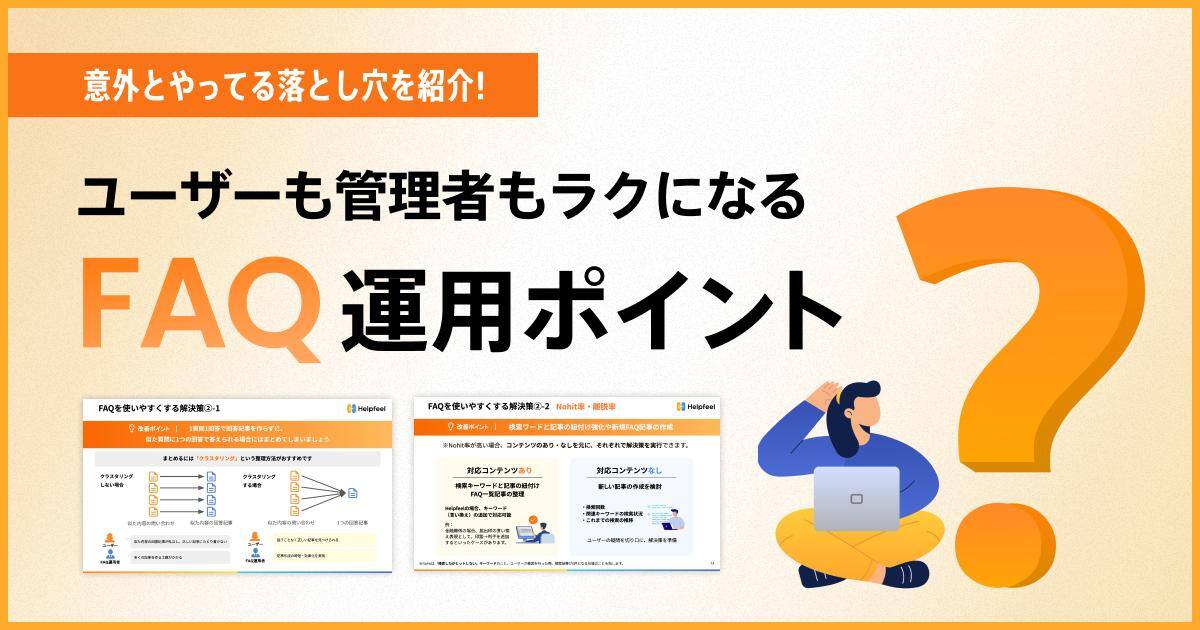
FAQシステムの活用で、月1.5万件あった問い合わせが半数以下に
地域内で人と人を結びつけるサービス「ジモティー」を運営する株式会社ジモティーは、FAQシステムの導入によって問い合わせ数を半減させ、業務品質の向上だけでなく人件費の削減も達成しました。
同社は最大で月間1.5万件の問い合わせがあり、24時間以内に返信する決まりを守ることで精一杯の状態でした。自社のFAQサイトは検索性が低く、改善しても問い合わせ数の削減には限界があったとのことです。
そこでFAQシステムを導入したところ、検索性の向上やデータに基づいたFAQページの改修により、顧客の利便性が向上。問い合わせ数が半減し、担当者の問い合わせ対応時間が4割も削減されて、個別対応が必要な問い合わせに時間を使えるようになりました。
FAQで即時に自己解決できるようになり、担当者の対応品質も上がったことで、顧客満足度の上昇も見られたそうです。
表記ゆれに強いFAQシステムを導入、膨大なFAQページを整理しメンテ負荷を削減
デジタルサービスに注力している株式会社伊予銀行は、FAQシステムの導入で顧客が求めるFAQページに辿りつきやすくなり、自己解決の促進とメンテナンスの効率化に成功。担当チームの人員削減も実現しています。
同社ではFAQサイトの閲覧数が多かったものの、検索性が低く改善の余地がありました。しかし、約800ページに及ぶFAQページの分析や、メンテナンスの負担が非常に大きな課題でした。
そこで表記の揺れに強いFAQシステムを導入したところ、目的のFAQページに辿り着ける確率が50%から70%に大きく改善。さらにFAQページのメンテナンス時間を月15時間も削減でき、他の業務に時間を使えるようになり、担当チームを3名から2名に縮小できました。
まとめ
ヘルプデスクは大きく分けて社外ヘルプデスク・社内ヘルプデスクの2種類があり、顧客や従業員の疑問や質問に対応するなど、さまざまな役割を果たしています。
ヘルプデスクがたびたび抱える課題を解決するなら、ITツールの活用が有効です。過去の問い合わせ事例やノウハウを共有して担当者のスキルを高め、問い合わせ数を減らすことができるでしょう。その結果、ヘルプデスクの運営課題を解決し、業務品質や対応品質の向上も期待できます。
Helpfeelでは検索性が高く、導入・メンテナンスが容易なFAQシステムを提供しています。さまざまな業界での導入事例もありますので、ヘルプデスクの品質向上に取り組みたい方は是非ご相談ください。