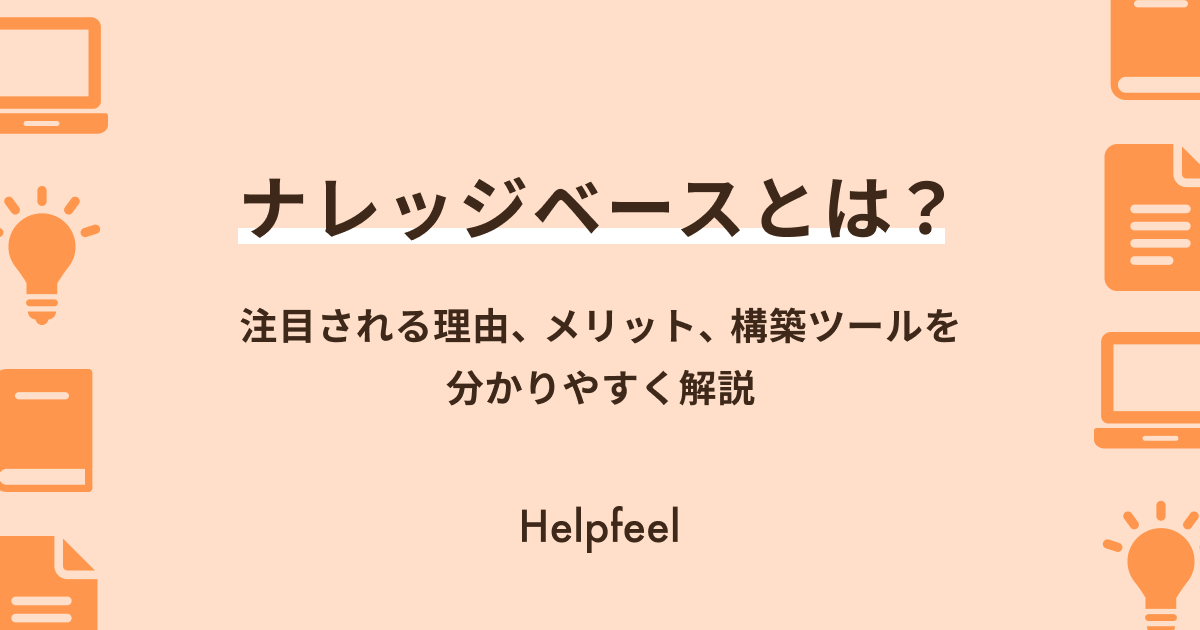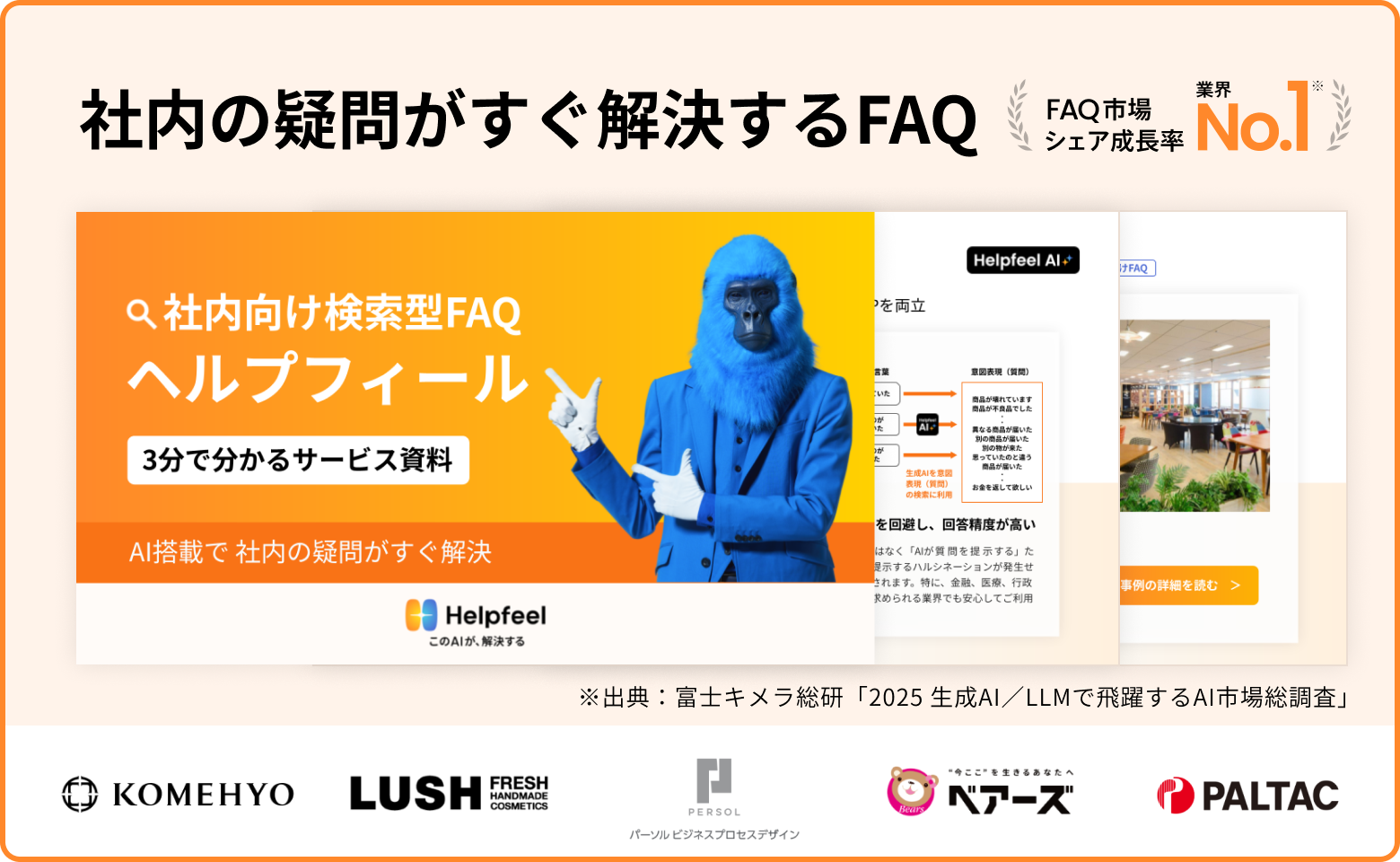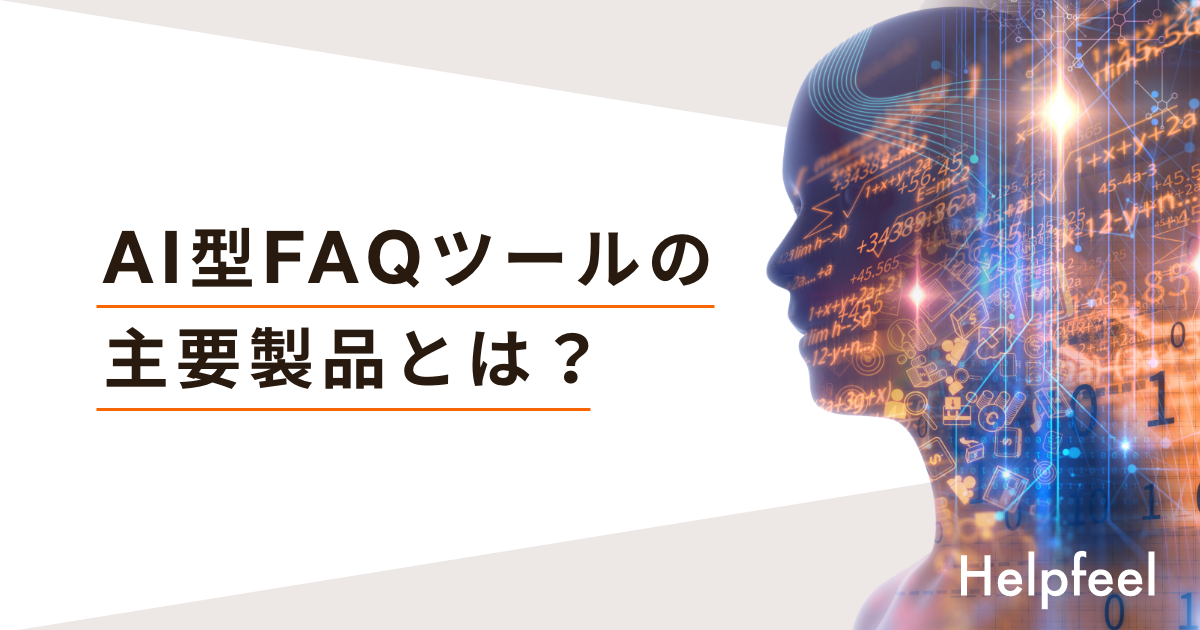ナレッジベースを作る前に押さえておくべきポイント
ナレッジベースを効果的に活用するには、基本設計を事前に固めておくことが重要です。
利用する人や目的を明確にし、運用後に成果を測るための指標(KPI)をあらかじめ決めておくことで、作成後の改善や活用もスムーズに進められます。
ここでは、ナレッジベースを「使ってもらえるもの」にするために、初期段階で意識しておきたいポイントを紹介します。
▼ナレッジベースの詳細な説明は、下記のコラムで詳しく解説しているのであわせてご一読ください。
「誰のために」「何のために」作るのかを明確にする
ナレッジベースを作り始める前に大切なのは、「誰が使うのか」「どんな目的で使うのか」を明確にすることです。例えば、技術部門と営業部門では、必要とする情報の種類や深さが異なります。それぞれのチームが本当に必要としている内容を見極めることが、活用されるナレッジベースにつながります。
目的をはっきりさせることで、どんな情報を優先して整備すべきか、更新の基準は何か、といった運用面の方針も決めやすくなります。
新入社員の教育、業務効率の改善、ノウハウの共有、社内ヘルプデスクへの問い合わせ件数削減など、自社の戦略に沿ったゴールを設定することで、ナレッジベースはより価値のある仕組みになるでしょう。
KPIを決めておく
ナレッジベースの作成後は、「きちんと効果が出ているか」を確認できるようにしておくことが大切です。そのために、あらかじめ成果を測るための指標(KPI)を設定しておきましょう。
例えば、「新入社員のオンボーディング期間を短くする」「ヘルプデスクへの問い合わせ件数の削減」「顧客対応に割く時間の削減」といった具体的な項目に対して数値目標を設定しておくと、ナレッジベースの活用度合いを客観的に評価できます。
定期的にKPIをチェックして、改善が必要なポイントを見直していくことで、より実用的で価値のあるナレッジベースに育てていくことができます。
小さく始めてスモールサクセスを目指す
ナレッジベースは、最初から完璧を目指すよりも、必要性の高いところから小さく始めるのが成功の近道です。
例えば、新人研修用のマニュアルや、よくある問い合わせへの回答など、日々の業務に直結する情報から着手することで、すぐに効果を実感できます。
こうしたスモールサクセスを積み重ねることで、ナレッジベースの有用性に対する社内での信頼が高まり、他のメンバーの参加意欲や情報を定期的に更新する文化の醸成につながります。
ナレッジベースの作り方【3つのステップ】

ナレッジベースを効果的に活用するには、「どんな情報を集め、どう整理し、どう運用するか」という全体のイメージを持っておくことが大切です。
情報をただ追加していくだけではなく、構造の設計や検索性、活用のしやすさまで含めた仕組みとして整えることで、継続的に活用されるナレッジベースが実現します。
ここでは、ナレッジの収集から情報の整理・構造化、ツール選びに至るまで、実践的な3つのステップを紹介します。
ステップ1:ナレッジを収集する
ナレッジベース構築の第一歩は、社内に散らばる知識や情報を拾い集めることから始まります。
マニュアルやドキュメントだけでなく、経験豊富な従業員の知見や、過去のプロジェクトの記録、業務の中で生まれた小さな気づきなど、価値ある情報はさまざまな場所に散らばっています。
特に重要なのは、属人化しているノウハウを明文化して共有することです。インタビューやヒアリングを通じて、普段は言語化されていない知見を掘り起こし、誰もが使える形に整えることで、チーム全体のナレッジとして活用できるようになります。
ステップ2:情報を構造化する
集めた情報をそのまま並べるだけでは、ナレッジベースとして十分に機能しません。必要なのは、読み手にとってわかりやすい形で情報を整理・構造化することです。これにより、探しやすさと管理のしやすさの両方を実現できます。
例えば、1ページにつき1トピックを扱う形式にすると、情報が簡潔になり他のページとの関係性も把握しやすくなります。カテゴリやタグを使って関連性のある情報をグループ化するのも一つの方法です。
組織や目的により最適な形は異なりますが、共通して大切なのは「誰が見てもわかりやすい構造」にすることです。
ステップ3:適切なツールを選ぶ
ナレッジベースを継続的に運用していくには、適切なツールの選定が欠かせません。検索のしやすさや更新の手軽さ、他システムとの連携など、使いやすさと拡張性を兼ね備えたものを選ぶことがポイントです。
検索機能が充実していれば、利用者は目的の情報にスムーズにたどり着けますし、直感的に操作できれば、誰でも気軽に記事を追加・修正できます。Helpfeelなどの社内向けにも使えるAI-FAQ型ツールや社内ドキュメント管理ツールなど、自社の環境や目的に合わせて最適なものを選びましょう。
▼ナレッジベースの構築・管理ツールについては、下記のコラムでも詳しく解説しているのであわせてご一読ください。
ナレッジベースの価値を高める運用・改善方法
ナレッジベースは構築して終わりではなく、「育て続ける」ことが大切です。定期的な見直しや更新を行える体制を整え、改善サイクルを回しましょう。
ここでは、ナレッジベースを長く使ってもらうために実践したい、運用と改善のポイントを紹介します。
定期的な更新体制を整える
業務フローや制度の変更、ツールのアップデートなどにより、ナレッジベースの情報は次第に古くなっていきます。情報を最新の状態に保つための更新体制を整えておくことが重要です。
「誰が、どの情報を、いつ見直すか」といった役割分担やスケジュールを明確にしておくと、更新が属人的にならず、習慣として定着しやすくなります。運用をルーティン化できれば、情報の信頼性も高まり、日常的なナレッジベースの利用につながります。
利用者からのフィードバックを集める
ナレッジベースをより実用的なものに育てていくためには、実際に使っている人の声を積極的に取り入れることが欠かせません。現場の「ここが分かりづらい」「こういう情報が欲しい」といったフィードバックは、改善のヒントになります。
記事ごとにフィードバック機能をつけたり、定期的なアンケートを実施したりすることも有効です。収集したリアルな声をもとに記事の加筆・修正を行えば、使う人が価値を感じられるナレッジベースに進化していきます。
利用状況を分析し、改善ポイントを見つける
ナレッジベースをより良くしていくには、どのような情報がどのように使われているかを客観的に把握することが重要です。
アクセス数、検索キーワード、滞在時間などのデータを確認することで、ユーザーがよく参照している記事や、うまく情報にたどり着けていないポイントが見えてきます。
例えば、「検索されているのにクリックされていない記事」や「閲覧後すぐに離脱されるページ」があれば、改善の優先度が高いコンテンツとして見直すきっかけになります。データを活用して改善サイクルを回すことで、ナレッジベースの価値は継続的に高まっていきます。
おすすめは「FAQ」を軸にしたナレッジ活用
 ナレッジベース全体を一度に整備するのは簡単ではありませんが、取り組みやすく、効果が見えやすいのが社内向けの「FAQ(よくある質問)」です。FAQを作成し改善していくことは、社内で埋もれている知識の掘り起こし、明文化につながるため、ナレッジベース作りのファーストステップとしておすすめです。
ナレッジベース全体を一度に整備するのは簡単ではありませんが、取り組みやすく、効果が見えやすいのが社内向けの「FAQ(よくある質問)」です。FAQを作成し改善していくことは、社内で埋もれている知識の掘り起こし、明文化につながるため、ナレッジベース作りのファーストステップとしておすすめです。
FAQが知識共有の起点に
FAQの整備は、問い合わせ対応の効率化に加えて、業務の標準化にもつながります。対応方針や手順が明文化されることで、誰が行っても同じ品質を保てるようになるためです。
単なるQ&Aの羅列ではなく、質問の背景や関連情報、具体的な対処法もあわせて記載することで、より価値のあるものとなるでしょう。整備されたFAQは、新人教育や業務の引き継ぎ、トラブル対応などに活用でき、組織内のナレッジ共有の起点として機能します。
Helpfeelでナレッジを“見つけやすく”
FAQを整備するうえで重要なのが「検索性」です。どれだけ良い情報を掲載していても、ユーザーが見つけられなければ意味はありません。
弊社が提供する「Helpfeel Back Office」は、ユーザーが入力した言葉から検索意図を予測し、最適な回答に導く社内ナレッジ検索ツールです。独自の技術「意図予測検索」により、高い検索精度を実現しています。
検索クエリの分析や改善提案などの伴走支援も充実しているため、運用負荷を抑えつつ常に情報を最新の状態に保つことができます。継続的に使われるナレッジベースを構築するために、Helpfeelの導入を検討してみてはいかがでしょうか。