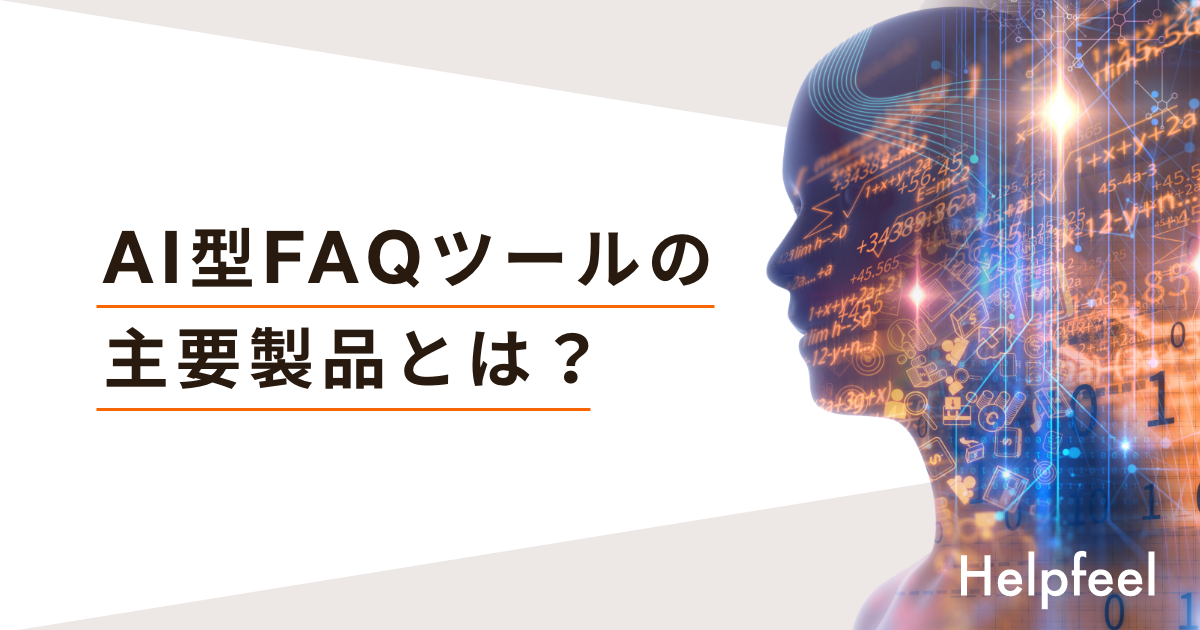社内ナレッジとは
社内ナレッジとは組織内で蓄積・共有され、いつでも活用できる状態に整備された知識や情報を指します。例えば、以下が該当します。
- 顧客情報や市場動向
- 成功事例・失敗から得た教訓
- 従業員が身につけた業務知識
- 各種業務マニュアル
一方、例え上記のような知識・情報であっても、組織内で活用できるように整備されていなければそれは「個人ナレッジ」に留まります。つまり“ナレッジを活用できるように整備すること”が重要なのです。
ナレッジとノウハウの違い
ナレッジと似た意味の言葉に「ノウハウ」があります。ノウハウとはナレッジと同様に「知識・情報」という意味が含まれますが、ノウハウは一般的に「ナレッジを踏まえて行動した結果として得られる知識・情報」と定義されます。つまりナレッジは、ノウハウを習得するための手段になると言えます。
社内ナレッジを蓄積、活用するメリット

では、社内ナレッジを蓄積・活用することでどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは4つのメリットを解説します。
業務効率化や業務負荷の軽減につながる
社内ナレッジは業務効率化および業務負荷軽減に寄与します。例えば、提案書や報告書などよく利用する資料テンプレートを社内で蓄積しておくことで、従業員はそれら資料をゼロから作成する必要がなくなります。
また、社内の各種申請手続きのフローを社内ナレッジに登録しておくことで、ミスや手戻りが減り、申請者および承認者の業務負担の軽減につながります。
効率的に業務を覚えられ、教育負荷を削減できる
社内ナレッジは人材育成においても有効です。例えば、業務マニュアルを社内ナレッジに蓄積しておけば、新入社員に業務の進め方や注意点などを円滑に伝えられるようになります。
そのほか、業務に関する成功事例や失敗事例を豊富に保存しておけば、毎回上司や同僚の助言を受けることなく、自己解決が図れる従業員が増えるでしょう。
業務の属人化を阻止しやすくなる
従業員それぞれが持つ主観的な個人ナレッジを、従業員全員が共有・活用できる客観的な社内ナレッジへと変換することで、業務属人化を防ぐ効果が期待できます。
業務の属人化が起こると、特定の従業員が休職・退職・異動した際に現場に混乱が起こる可能性があります。しかし社内ナレッジが適切に共有されていれば、そうした混乱を防ぎ、スムーズに業務の引き継ぎができるでしょう。
ミスを防ぎやすくなり、業務に関する安心感につながる
社内ナレッジの内容には、業務における改善点やミスの原因なども含まれます。そのため、他の従業員のナレッジによって事前につまずきポイントを把握でき、ミスを未然に防ぐことが可能です。こうして社内ナレッジがミス防止の施策として機能すれば、業務に対する安心感にもつながります。
社内ナレッジを効率的に蓄積するためのポイント

社内ナレッジを収集・蓄積する仕組み作りは、なるべく効率的に進めたいところです。そこで、社内ナレッジを効率的に蓄積するための4つのポイントを解説します。
ナレッジを蓄積する目的を共有し、重要性を理解してもらう
社内ナレッジの蓄積を新たな業務として加えると、日々忙しく働く従業員には「仕事が増えて大変だ…」と思われてしまうかもしれません。だからこそ従業員には、主体的にナレッジを蓄積するモチベーションを持ってもらう必要があります。
そのモチベーションの土台となるのが「なぜ社内ナレッジを蓄積するのか」という目的意識です。全従業員へ社内ナレッジを蓄積する目的を共有し、その重要性をよく理解してもらうようにしましょう。
蓄積するナレッジの方向性を定める
従業員にはどのようなナレッジを蓄積してほしいのか、企業として方向性を定めておくことも重要です。そうしないと従業員は「この情報は蓄積した方がいいのだろうか」と迷い、ナレッジを蓄積するペースが下がってしまうかもしれません。
蓄積するナレッジの方向性を定める際は、具体的に蓄積するナレッジの具体例を示すとともに、場合によってはナレッジ蓄積を推進する責任者「ナレッジリーダー」を設けることも有効です。
ナレッジを蓄積・共有しやすい環境を作る
一部従業員には「ナレッジの蓄積・共有は手間がかかる」と感じられてしまうかもしれません。そのため、ナレッジを蓄積・共有しやすい環境を作り、ナレッジ蓄積のハードルを下げることが重要です。
その取り組みとしては、ITツールの導入が有効です。ITツールを用いることで、ナレッジを蓄積するハードルと、ナレッジを検索するハードルを下げることができるからです。このふたつのハードルを低くすることで、ナレッジの蓄積・活用のさらなる加速が期待できるでしょう。
ナレッジ共有を定期的に呼びかける
施策スタート当初は積極的にナレッジを共有していた従業員でも、徐々に共有頻度が下がってしまうケースがよく見受けられます。ナレッジを継続して蓄積してもらうためには、従業員に社内ナレッジ共有の有用性を定期的に伝える取り組みが有効です。
定期的にアナウンスを行うなどして、社内ナレッジ蓄積が従業員自身にメリットがあることを伝えるとともに、社内ナレッジ蓄積に力を入れている企業の姿勢も示すとよいでしょう。
社内ナレッジを蓄積・共有する方法

続いて、社内ナレッジを蓄積・共有する具体的な方法を3つ解説します。
ナレッジ共有ツールの活用
ナレッジ共有ツールとは、業務に必要な知識や最新情報、マニュアルなどのナレッジを効率的に組織内で蓄積・共有するためのシステムです。
同ツールでは、ナレッジ共有手段として従来からよく使われるWordやExcelなどと比べて、情報を見つけやすい検索機能や手軽に情報を書き上げられる登録機能が充実しています。
加えて、社内Wikiや社内FAQを作成できるツールもあります。ナレッジ共有ツールは社内ナレッジを効率的に構築するにあたり、ぜひ導入を検討したいツールだと言えるでしょう。なおHelpfeelでは、ナレッジ共有ツール「Cosense」と社内FAQシステム「Helpfeel」を提供しています。
社内wikiの作成
社内wikiとは、組織内の知識や情報を整理した、いわゆる“社内版Wikipedia”です。社内wikiに従業員一人ひとりが情報を集積していくことで、より活用しやすい形で情報を蓄積することができます。
社内wikiは検索性が優れているため特定の情報を探しやすく、どこにどのような情報があるのかを把握しやすい点が特徴です。社内wikiの作成にあたっては社内wikiツールの導入が有効です。ツールを選ぶ際には、効率的な検索機能や権限管理機能などを踏まえて選定するとよいでしょう。
社内FAQの作成
社内FAQとは、従業員向けのよくある質問と回答を体系的に整理したものです。社内FAQを導入することで、各従業員が持つ知識やノウハウを社内ナレッジとして蓄積し、新入社員含むすべての従業員がその情報を活用することができるようになります。
また社内FAQは業務時間問わず閲覧できるため、業務時間外の予期せぬトラブルが発生した際にも社内FAQを参照して従業員自身で自己解決を図ることが可能です。
なお、社内FAQを作成するにはツールを導入する必要があります。ツールには表計算ソフトやチャットボットなどが挙げられますが、以下に該当する場合には、社内FAQシステムの活用が有効です。
- 社内FAQとして整備すべき質問回答の数が多い
- 社内FAQの導入、運用にかけられる人的コストが限られている
- 社内FAQを運用しているものの、問い合わせが減らない
- 社内FAQを運用しているが、使い勝手や検索機能に不満を持っている
上記のような悩みを持ち、高品質な社内FAQを作成したい場合には、社内FAQシステムの活用を検討しましょう。
▼本記事に関連したお役立ち資料もご用意していますので、ぜひ併せてご覧ください。

社内FAQを活用した社内ナレッジ蓄積の成功例

実際に社内FAQを導入して社内ナレッジを蓄積した企業では、どのような導入効果を得られたのでしょうか。
弊社では、最先端の検索テクノロジーを搭載した革新的なFAQシステム「Helpfeel」を開発・提供しています。Helpfeelを社内FAQとして導入された企業様では、問い合わせ率の削減や、運用コストの削減といった目に見える効果が出ています。
ここで、社内FAQを活用して社内ナレッジ蓄積を成功させた事例を紹介しましょう。
社内FAQの設置で従業員の満足度が向上!
卸売業を営む株式会社PALTACでは、2019年より社内FAQのAIチャットボットを設置していました。しかし、AIチャットボットは想定した質問内容を利用者が入力しないと回答にたどり着けない仕様であったため利用が思うように進まず、社用PCや社内システムに関する電話問い合わせが頻繁に発生していました。
そこで同社は2023年半ばより社内FAQをAIチャットボットからHelpfeelに切り替え。AIチャットボット利用時と比べ、社内FAQの利用回数は5.2倍にまで増加し、さらに担当者も電話による問い合わせ回数が大きく減少したことを実感しています。
なお、同社はHelpfeel導入の決め手について、「意図予測検索」によりさまざまな言葉から検索できる点や誰でも使いこなせるであろう使い勝手の良さを挙げていました。
専用ツールを活用し、社内ナレッジを効率的に蓄積・共有しよう
社内に散らばるナレッジを蓄積していくと、業務効率化や業務負荷の軽減が期待できます。注力すべき業務にリソースを投下できる環境を整えることも可能になるでしょう。
一方、社内ナレッジを蓄積する作業が必要になるため、従業員に一定の負荷がかかることも事実です。そのため、従業員がナレッジを登録するハードルを下げることが、社内ナレッジ運用成功のポイントになります。
本記事で紹介した「Helpfeel」は、手書きメモやメールのやりとりなどをそのままFAQのコンテンツとして活用することができます。独自の検索技術にAIをかけ合わせた検索機能など、社内ナレッジ運用を加速させる便利な機能も備えていますので、ぜひ活用をご検討ください。