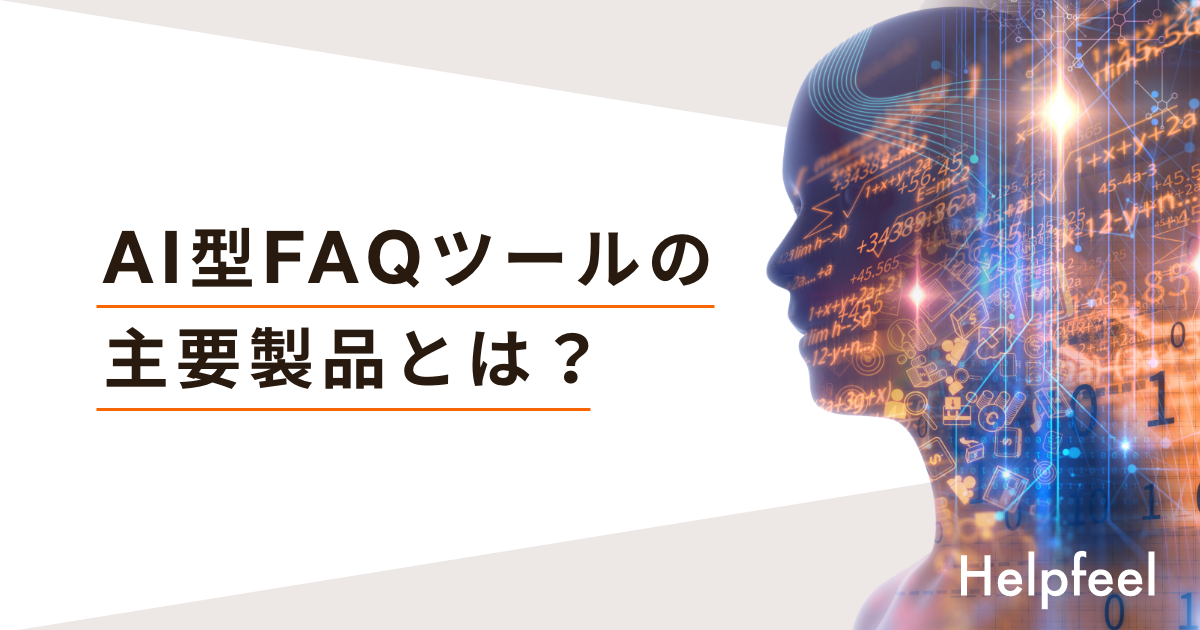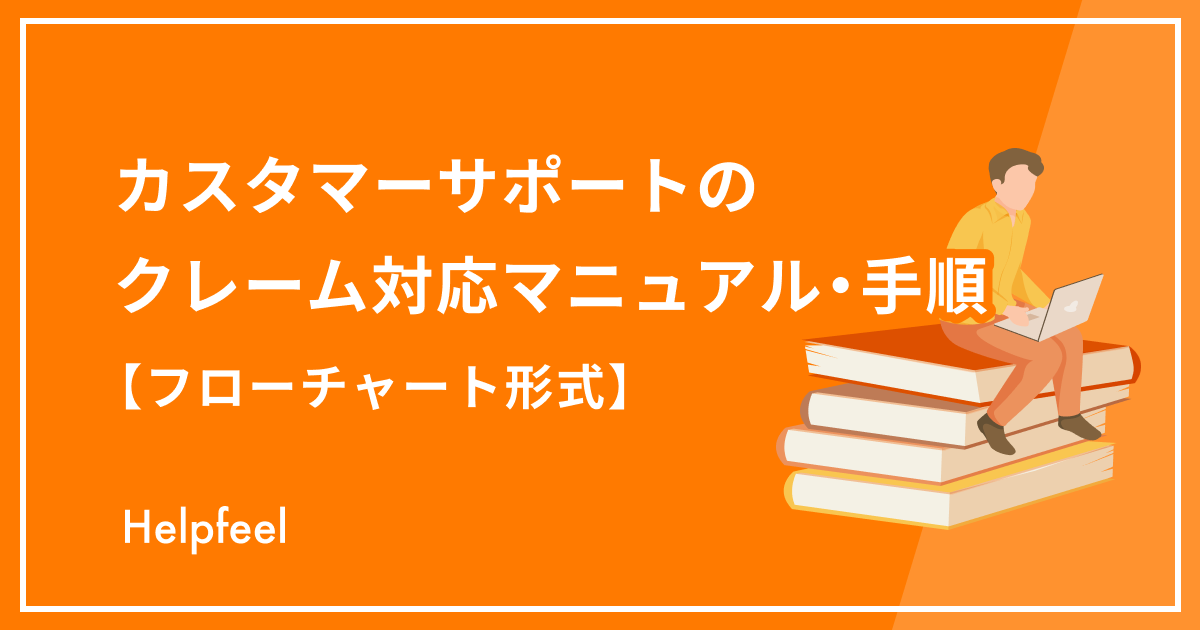NPS®️(ネット・プロモーター・スコア)とは

まずは「NPS®とは何か?」について、以下の3つに分けて解説していきます。
- NPS®︎とは
- NPS®︎の計算方法
- NPS®︎とCS(顧客満足度)の違い
それぞれ詳しく見ていきましょう。
NPS®︎とは
NPS®︎は「Net Promoter Score」の略称で、2003年にアメリカのベイン・アンド・カンパニーが提唱した「顧客ロイヤリティ」を測定するための指標です。
顧客ロイヤリティとは、企業や製品、サービスに対して顧客が抱く信頼や愛着の度合いを指します。このロイヤリティが高いほど、顧客はその企業やサービスをリピートしやすく、他人に勧める可能性も高くなります。
この顧客ロイヤリティを具体的に把握するために生まれたのが、NPS®︎です。NPS®︎を活用すれば、顧客がどれだけ信頼や愛着を感じているかが数値化でき、これまで見えにくかった顧客のリアルな評価が把握できるようになります。
注:ネット・プロモーター、ネット・プロモーター・システム、ネット・プロモーター・スコア、NPS、そしてNPS関連で使用されている顔文字は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、NICE Systems, Inc.の登録商標、またはサービスマークです。
▼顧客ロイヤリティについては別の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
NPS®︎の計算方法
「NPS®スコア」は、顧客の推奨度を数値化するシンプルな計算方法が特徴です。まず、「商品やサービスを家族や友人にどの程度勧めたいと思うか」を、0~10のスコアで尋ね、その結果を以下の3つに分類します。
- 9~10点を付けた回答者:推奨者
- 7~8点を付けた回答者:中立者
- 0~6点を付けた回答者:批判者
次に、回答者全体に占める推奨者の割合(%)と批判者の割合(%)を計算します。「推奨者の割合」から「批判者の割合」を引いたものが、NPS®スコアです。なお、スコアは、割合を省略して数値として表します。
NPS®︎とCS(顧客満足度)の違い
NPS®とCS(顧客満足度)は、いずれも顧客の心理を測定するものですが、目的や指標の性質が異なります。CSは現時点の満足度を評価する指標で、「満足」の範囲が広いので、業績や顧客離反と直接結びつかないことも少なくありません。
一方で、NPS®は「他人に勧めたいか」という未来志向の行動意図をスコア化するため、顧客のロイヤルティや企業収益と深い相関関係にあります。
また、NPS®では推奨者や批判者の割合を算出することから、ロイヤリティの高い顧客層を把握できます。NPS®は、CSよりも顧客との長期的な関係構築や成長戦略の指標として有用といえるでしょう。
▼CSについて、詳しく知りたい方は以下の記事を参考にご覧ください。
NPS®️を活用するメリット

NPS®を測定する前に、活用するとどのようなメリットがあるのかを理解しておいてください。
NPS®の活用メリットには、以下の3つがあります。
- 企業活動に生かせる
- 商品・サービスの改善が図れる
- 競合他社とスコアを比較できる
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
企業活動に生かせる
NPS®️は、企業活動において成長と収益向上を支える重要な指標です。NPS®️スコアを向上させるためには、顧客が「勧めたくない」と感じる要因を解消し、「勧めたい」と思わせる価値を提供することが不可欠です。
継続してNPS®️を測定し、改善を続けていくことで、リピート購入や口コミを通じた新規顧客の獲得につながります。NPS®️スコアの改善は顧客ロイヤルティの向上に直結し、自然と業績もアップするでしょう。
商品・サービスの改善が図れる
NPS®️を活用することで、商品やサービスの改善に効果的なアプローチが可能になります。NPS®️のアンケート調査では、顧客が感じている満足点や不満点を数値化するだけでなく、その理由を「自由回答」として収集することが一般的です。
自由回答を収集すると、顧客が何を評価し、どの部分に改善を求めているのかが明確に把握できます。例えば、「使い勝手が良い」という評価があれば、製品の改善につなげることが可能です。一方で、「対応が遅い」という指摘があれば、サポート体制の見直しが有効な一手となるでしょう。
競合他社とスコアを比較できる
NPS®️を活用することで、競合他社と自社の顧客ロイヤルティを比較できる点が大きなメリットです。NPS®️は、業界や企業を問わず、質問内容や評価方法が統一されているので、同じ基準でのスコアが比較できます。
そのため、自社が業界内でどの位置にいるのかを一目で把握できます。例えば、競合に比べて低いスコアがあれば改善点を特定でき、競争力強化につなげられるでしょう。
NPS®️調査を実施する5ステップ

自社のNPS®️スコアを測定するには、進め方を把握しておくことが重要です。NPS®️の調査は、以下の5つのステップで進めていきます。
- 調査の目的を明確にする
- アンケートの手法を決める
- 質問内容を抽出する
- 結果を分析する
- 分析結果から改善施策を施す
調査の目的を明確にする
まずは、NPS®️調査の目的を明確にしましょう。目的を定めることで、調査の焦点が明確になり、具体的かつ有益な質問を設定できます。
例えば、ブランド全体の推奨度を把握するのか、特定の接点や体験の満足度を測定するのか、あるいは顧客が抱える課題を特定するのかといった目的によって、質問の内容や形式が異なります。
目的を事前に設定しておくことで、活用方法に合ったアンケート結果が得られるためです。
アンケートの手法を決める
次に、NPS®️アンケートの手法を決定します。主な手法には、「トランザクション調査」と「リレーショナル調査」の2つがあります。
トランザクション調査
トランザクション調査とは、顧客の体験直後に行う調査で、具体的な利用シーンに基づいた評価を収集する手法です。例えば、購入手続きやサポート対応の完了後、すぐにフィードバックを求めることで、顧客の感情や満足度をリアルタイムで把握できます。
瞬間的な体験の質を評価し、特定のプロセスやタッチポイントでの改善点を明らかにするために有効です。
リレーショナル調査
リレーショナル調査は、顧客が自社ブランドに対して抱いている全体的な印象や関係性を評価する手法です。顧客がブランドと接するさまざまなシーンを通じて形成された総合的な満足度やロイヤルティを測定します。
個別の体験に焦点を当てるのではなく、ブランドとの長期的な関わりの中での全般的な評価を尋ねるという点が特徴です。年に1、2回など、定期的な実施がおすすめです。
質問内容を抽出する
NPS®️アンケートでは、質問内容の選定も重要なポイントです。まず、幅広く質問をリストアップして、顧客体験全体をカバーできるような質問を準備しましょう。
このとき、顧客の購買行動やサービス利用の流れを理解するために、カスタマージャーニーマップを活用するのが有効です。カスタマージャーニーマップを参考にすれば、顧客がどのような接点でどのような課題や期待を持つのかを具体的に把握できます。
また、質問数が多過ぎると途中で離脱者が出る恐れがあるので、重要な質問に絞り込むことが必要です。回答率を向上させつつ、回答データの質を高めていきましょう。
結果を分析する
アンケート実施後は、結果の分析へと移ります。分析方法には、定性分析と定量分析の2つがあります。
定性分析
定性分析は、数値化が難しいデータを解釈し、深い洞察を得るための分析手法です。NPS®️アンケートでは、コメント欄に「その評価の理由を教えてください」と記載し、顧客の自由回答を収集します。
集まったコメントは、共通点やテーマごとにカテゴライズし、「推奨者」「批判者」「中立者」の各グループの特徴を明確にしていきましょう。コメントをポジティブとネガティブに分類することで、顧客が評価するポイントや改善を求める課題が具体的に浮かび上がり、サービス向上の指針が決まります。
定量分析
定量分析は、数値データを活用して物事を評価・分析する手法です。NPS®️アンケートで定量分析を行う場合、推奨度と関連する他の評価項目のデータを用いて、相関分析などの手法を活用するのが効果的です。
例えば、推奨度と満足度を数値で回答してもらい、データをチャート化することで、顧客がどの要素に満足し、どの部分に不満を抱えているのかを視覚的に把握できます。定量分析を行うことで、具体的な改善ポイントを特定しやすくなり、顧客体験の向上につなげることが可能です。
分析結果から改善施策を施す
NPS®️スコアを算出した後は、分析結果を基に、課題の改善や強みの強化を進めていきます。スコアが低い場合は、サービスそのものに対する顧客の愛着が低い可能性があるため、製品やサービスの根本的な見直しは不可欠です。
また、分析を通じて自社の強みを明確にし、その強みをさらに伸ばす施策も効果的です。この改善と強化のサイクルを継続することで、NPS®️スコアが向上し、顧客ロイヤルティが高まり、結果的に収益の向上が期待できるでしょう。
NPS®️活用の効果を高める3つのコツ

NPS®️を測定するなら、最大限に利用したいものです。NPS®️活用の効果を高めるためのコツには、以下の3つがあります。
- 定性分析・定量分析のどちらも実施する
- 競合と比較する
- 継続して測定する
定性分析・定量分析のどちらも実施する
NPS®️を活用するには、定性分析と定量分析を組み合わせて実施しましょう。定性分析の自由回答からは、顧客が感じている課題や評価点を深く理解することが可能です。
一方で、各要素の満足度と推奨度の相関を測定した定量分析は、顧客ロイヤルティに与える影響力を数値化するために欠かせません。
定性分析と定量分析の2つのアプローチは補完関係にあり、どちらか一方だけでは不十分です。2つを併用することで、顧客体験を包括的に理解し、NPS活用の精度を高められます。
競合と比較する
NPS®️を効果的に活用するためには、競合企業と比較してみることが重要です。NPS®️スコアは、単独で見ると数値の高低に一喜一憂しがちですが、それだけでは十分な評価はできません。
例えば、NPS®️がマイナスであっても、業界全体の傾向であれば、必ずしも深刻な問題とはいえないことがあります。競合他社のスコアと比較することで、自社の強みや改善が必要な点を相対的に理解できるでしょう。競合他社と比較することで、自社の進むべき方向性をより具体的に見極められます。
継続して測定する
NPS®️調査の効果を最大化するには、継続して実施してください。一度測定しただけでは、その時点の状況しか把握できません。定期的に実施することで、顧客のロイヤルティや満足度の変化を時系列で追跡できます。
継続して測定することで、自社のマーケティング手法や改善施策が適切に機能しているかを確認できます。また、顧客のニーズや市場の変化に応じて調査項目を定期的に見直すことで、より実用的なインサイトが得られるでしょう。
NPS®︎を上げるにはFAQの改善も効果的
NPS®️を上げるためには、顧客満足度の向上が欠かせません。顧客が商品やサービスを利用する中で生じる疑問や問題には、迅速かつ効果的に対応することが大切です。そこで役立つのが、FAQシステムの活用です。
「Helpfeel」は、直感的に使えるAI搭載のFAQシステムで、顧客が必要な情報を素早く自己解決できる環境を構築するのに最適です。特許技術による高度な検索機能が備わっており、問い合わせ窓口の混雑によるストレスを軽減できます。その結果、顧客体験が向上し、NPS®️の改善にもつながります。
顧客満足度を向上させNPS®️を高めるためにも、Helpfeelの導入をぜひ検討してください。
まとめ:NPS®︎を活用して顧客満足度の向上を図ろう

NPS®️は、顧客ロイヤルティを数値化し、自社の強みや課題を明確にする強力な指標です。競合他社と比較しやすいので、自社の立ち位置を把握し、適切な改善策を講じるためにも欠かせません。また、推奨者を増やすことで顧客満足度やリピート率を高め、収益向上も期待できます。
NPS®️を活用することで、競合に差をつける具体的なアクションが見えてくるはずです。顧客体験を向上させるためにも、NPS®️の測定と活用をぜひ始めてみてください。