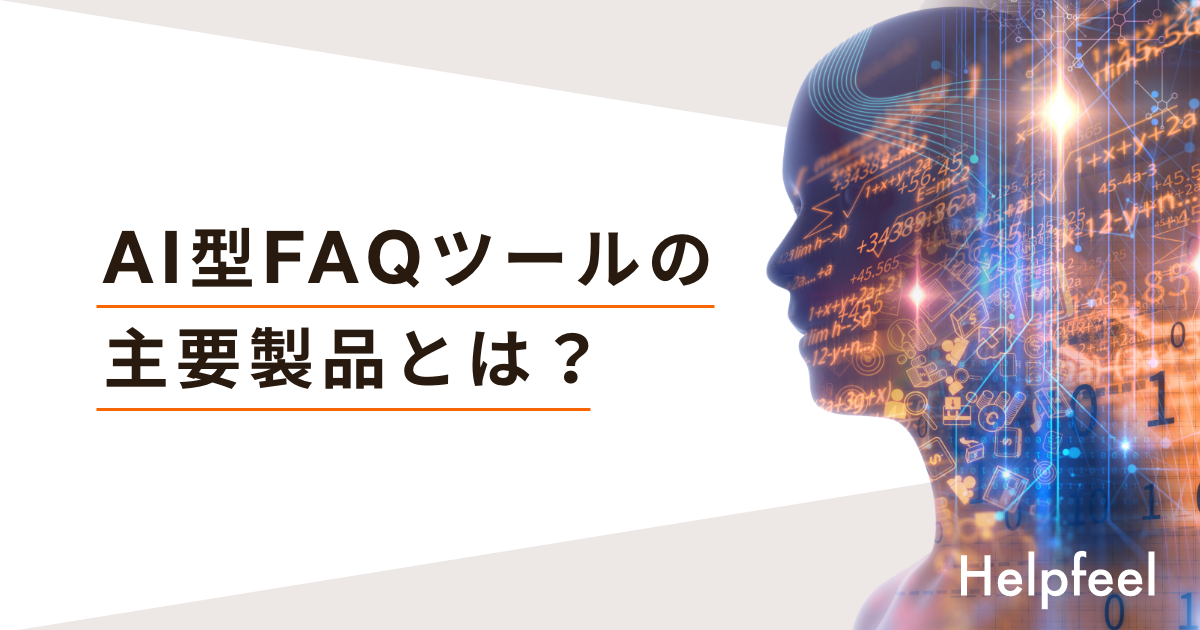社内Wikiが失敗する理由5選

社内Wikiの導入が失敗する5つの理由について、詳しく紹介します。
- 導入の目的が明確になっていない
- ツールが使いにくい
- 運用方法が決まっていない
- 情報共有の文化が根付いていない
- 投稿に時間がかかる
導入の目的が明確になっていない
社内Wikiを導入する目的を明確にしていないと、システムが形骸化します。なぜ社内Wikiが導入されたのか社員が理解していないため、社内Wikiの活用に消極的になるからです。
これから社内Wikiを導入する際には、目的を明らかにした上で社員に周知することが重要です。業務上の重要な情報やノウハウを共有する仕組みであると周知し、社員が社内Wikiを活用したいと思えるような雰囲気を作ることが大切です。
ツールが使いにくい
導入した社内Wikiのツール・システムが使いにくいために、利用者が増えないケースがあります。知りたい情報を検索する方法や、共有したい情報を加える方法などが分かりにくいと、社内Wikiを業務で活用することが難しくなるでしょう。
社内Wikiツールを導入する場合は、事前に操作性を確かめ、評判を調べることをおすすめします。パソコンが苦手な社員でも利用できるように、簡単で分かりやすいツールを選ぶことも大切です。
また、パソコンだけではなくスマートフォンやタブレットからも扱いやすいかどうかも着目しましょう。デバイスによらず使いやすいツールであれば、外出中の社員も社内Wikiを積極的に活用するはずです。
▼社内Wikiについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
運用方法が決まっていない
社内Wikiの運用方法が定まっていないと、社員がツールの使い方に迷ってしまいます。例えば、投稿のタイミングや書き方などのルールが明確でない場合は、社内Wikiをどのように業務へ生かすべきか分からず、社員が混乱するためです。
そのため、あらかじめ社内Wikiへの書き込みのテンプレートを用意しておき、記載すべき内容についてルールを設けておきましょう。また、書き込みをするタイミングや更新に関するルールも明確にしておくことが大切です。
運用方法が明確であれば、社員が積極的に社内Wikiを活用するようになり、社内Wikiの内容は充実します。
情報共有の文化が根付いていない
社員同士で情報を共有する文化が根付いていないと、社内Wikiを導入しても活用されない状況に陥ることがあります。社内Wikiを導入する際には、ナレッジ共有をする文化を醸成することが大切です。
例えば、社内Wikiを社員に周知した上で、管理職など影響力のある人が積極的に投稿するなどの方法も効果があります。また、勉強した内容や成功事例など、価値のある情報を積極的に投稿しておくと、社内Wikiの価値を認識しやすくなるでしょう。
「報告書や会議資料などは社内Wikiに必ず投稿する」とルールに定めるなど、強制的に利用する機会を作っておくのも効果的です。
投稿に時間がかかる
投稿に時間がかかる社内Wikiでは、社員が利用に消極的になる場合があります。投稿作業そのものが業務の負担になるケースがあるためです。
業務時間を超えてまで投稿作業をしたいと考える社員は少ないため、手間がかかると投稿数が減少するケースも考えられます。
投稿にかかる時間を短縮するには、事前に投稿ルールを明確にしておくことが重要です。また、投稿する際に入力すべき項目を絞り込んでおくと、スムーズに投稿できるようになります。
あらかじめテンプレートを用意しておくと、項目を埋めていくだけで内容が完成するため、投稿時間の短縮につながるでしょう。
社内Wikiで失敗しないための対策

社内Wikiの導入で失敗しないための、5つの対策を紹介します。
- 導入目的を明確にする
- 積極的な活用を促す
- 操作性のよいツールを選ぶ
- 運用ルールを策定する
- 情報は社内Wikiに集約する
▼社内Wikiの作り方について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
導入目的を明確にする
社内Wikiの導入を進める目的を明確にしておくと、現場に定着しやすくなります。企業や現場が抱える課題を解決する手段として、社内Wikiの活用が効果的だと納得してもらえるためです。
社内Wikiを導入する目的として一般的なものを、以下にまとめました。
- 情報共有の促進
- 属人化の解消
- ナレッジの一元化
- 人材育成の効率化
- コミュニケーションの促進
それぞれの企業・現場が抱える課題を踏まえた上で、社内Wikiの導入目的を明確にしておきましょう。
社内Wikiの導入を進める際には、導入目的を明示して周知させることで、社員が目的意識を持って社内Wikiを利用してもらえるようになります。
積極的な活用を促す
社内Wikiが社内で活用されるように、積極的に促すことが重要です。例えば、社内Wikiの利用者を評価する制度を設けてモチベーションを高めるという対策が考えられます。
投稿した数や内容の質などで投稿者のランキングを発表し、上位者には表彰するといった方法も効果的です。
また、社内Wikiに貢献することで直接的なインセンティブを与えるという方法もあります。投稿の件数に応じた報酬を受け取れる制度があれば、積極的に投稿する社員を増やせるでしょう。
社内Wikiの利用が利益につながる仕組みを整えることで、社内Wikiの活性化が期待できます。
操作性のよいツールを選ぶ
操作性の優れたツールを選ぶことで、社内Wikiの利用率を高めることができます。
専門知識が不要で、操作性がシンプルで、短時間で投稿を完了できるツールが望ましいでしょう。直感的に利用できるツールであれば、社内Wikiの活用率を向上させることができます。
トライアル版が用意されているツールであれば、社員に試用してもらい、操作性を評価してもらうことをおすすめします。また、公式サイトにアクセスして、操作画面や利用方法などを確認することも大切です。
全社員が使用することを踏まえて、ITリテラシーが低い社員でも問題なく扱えるツールを選びましょう。
運用ルールを策定する
社内Wikiの作成や、投稿などに関する明確な運用ルールを策定することは重要です。明確なルールが設けられていれば、社内Wikiを利用するときの迷いが生じにくくなります。
設定しておきたい運用ルールの具体例は、投稿内容、投稿タイミング、カテゴリー分けの仕方などです。議事録や報告書など、必ず投稿しておく事柄を決めておくと、社内Wikiの利用を促せます。
また、必要に応じて社内Wikiの作成や閲覧の権限を設けておくことも大事です。アクセス権を設定しておくことで、機密性の高い情報が漏えいするのを防げます。
ただし、運用ルールを細かく策定すると混乱を招くため、ルールの設定は最低限にとどめておきましょう。
情報は社内Wikiに集約する
社内Wikiを導入する際には、原則として全ての情報を社内Wikiに集約させることが大切です。紙の資料で管理している情報や別のツールで管理している情報などを、社内Wikiで閲覧できる状態にしておきます。
情報を一元化することで必要な情報にすぐアクセスできるようになり、社内Wikiの利便性は高まるでしょう。ペーパーレス化を進めるのにも効果的で、資料の印刷・保管コストの削減につながります。
ただし、全ての情報をデータ化して社内Wikiに集約するまでには膨大な時間がかかることも珍しくありません。少しずつデータ化を進めていき、社内Wikiの情報を充実させていきましょう。
▼本記事に関連したお役立ち資料もご用意していますので、ぜひ併せてご覧ください。
.webp)
失敗しない社内Wikiを選ぶポイント

社内Wikiのツール選びで失敗しないために重要なポイントを、5つ解説します。
- 必要な機能はあるか
- 操作性はよいか
- 検索性は高いか
- 費用は適切か
- セキュリティは高いか
必要な機能はあるか
社内Wikiに必要な機能が全てそろっているかどうかに注目して、ツールを選びます。社内Wiki導入の目的を明確にし、使用する状況を踏まえた上で必要な機能をリストアップしましょう。
どんな機能が必要になるのか分からない場合は、現場の社員へヒアリングすることも大切です。現場の意見を参考にすれば、本当に必要とされる機能を備えたツールを選べるため、社内Wikiが浸透しやすくなるでしょう。
例えば、外出先でも利用したいという意見があれば、マルチデバイスに対応したツールを選びます。
機能が多すぎると不要なコストがかかり、使いにくくなる点には注意が必要です。必要な機能のみが搭載されたシンプルなツールを選定することをおすすめします。
操作性はよいか
社内Wikiを選ぶ際には使いやすさを重視し、操作性に注目することが大事です。ITに対して苦手意識のある社員でも問題なく利用できるツールを選びましょう。
投稿や検索、閲覧など基本的な機能が直感的に利用できるUIを採用しているツールであれば、ITリテラシーの低い社員にも配慮できます。
また、ユーザーガイドが充実しているか、導入後の技術サポートがあるかどうかも重要です。操作方法について分かりやすく説明しているユーザーガイドがあれば、疑問点をすぐに解決できます。使い方を説明する動画コンテンツなどがあると、操作方法を確認しやすいです。
検索性は高いか
社内Wikiを選ぶ際には、検索性の高さが重要です。社内Wikiに掲載される情報が増えると、検索機能を使って目的の情報を探さなければなりません。検索機能が充実していて、検索の精度が高いツールであれば、目当ての情報がすぐに見つけられます。
検索性の高いツールには以下のような機能が備わっていることが多いです。
- キーワード検索:単語やフレーズで簡単に検索可能
- 組み合わせ検索:複数の条件を指定して検索結果を絞り込み可能
- グループ検索:特定の部署やプロジェクト単位で検索可能
検索性が高いとストレスなく利用できるため、社内Wikiが社内に浸透しやすくなるでしょう。
例えば、キーワード検索や組み合わせ検索、グループ検索など複数の検索機能が備わっていると便利に使えます。
AIが搭載されていて、入力した文章の意味や文脈を活用した高度な検索機能ができるツールもあるため、検討してみましょう。
費用は適切か
社内Wikiを利用するのにかかる費用が適切かどうか、判断することは重要です。
社内Wikiのツールは利用人数や機能に応じたプランが用意されていて、料金には幅があります。一般的に、利用人数が多い場合や、機能が豊富に備えられているツールは高い傾向にあります。
ツールの導入前に以下のポイントを整理しておきましょう。
- 利用人数:ツールを利用する従業員の人数
- 必要な機能:検索性やセキュリティ性、カスタマイズ性など
- 予算:月額や年間でどれくらいの費用を想定しているか
利用する人数や使いたい機能を確認し、費用のバランスを比較検討することが重要です。
事前に希望する条件をまとめた上で、ツールごとに費用をシミュレーションしてみてください。各ツールの費用を比較することで、費用対効果の優れたツールを見つけられるでしょう。
必ずしも料金の高いツールが優れているとは限りません。現場の状況や予算を踏まえた上で、適切な条件のツールを探しましょう。
セキュリティは高いか
社内Wikiは機密性の高い情報が多く保管されるため、セキュリティの高さは重要です。
どのようなセキュリティ対策が施されているのか、セキュリティの国際規格を取得しているかなどを重視してください。
セキュリティが高いか判断するために以下のような機能に注目しましょう。
- 二段階認証:不正アクセス防止
- アクセス権限管理:情報の閲覧・編集権限を制限
- 国際規格の認証:ISO27001などの情報セキュリティ規格を取得しているか
例えば、二段階認証の機能があるツールならば、不正アクセスの防止に効果的です。ISO27001など、情報管理に関連した国際規格の認証を受けているかもチェックしましょう。
アクセス権限の設定ができるかどうかも大事です。機密情報が誰でも閲覧できる状況はリスクがあるため、アクセス権限を適切に制限することで情報漏えいのリスクを低減できます。
社内Wikiでの失敗が続くときにはナレッジ検索ツールの併用がおすすめ
社内Wikiの導入がうまくいかない場合には、ナレッジ検索ツールとの併用をおすすめします。ナレッジ検索ツールにより必要な情報をすぐに見つけられるようになり、情報共有の状況改善が期待できます。
「Helpfeel」はAIを活用したFAQシステムで、独自の検索技術とAIを組み合わせているのが特徴です。ナレッジを自動で作成できる機能もあり、精度の高い回答を提示してくれます。
Helpfeelを導入すれば、社内Wikiと併用することで社員の情報共有への意識を高められるでしょう。Helpfeelの導入に興味のある方は、サービス資料をご覧ください。
まとめ:情報共有を促して社内Wikiの失敗を防ぎましょう

本記事では、社内Wikiの導入が失敗する原因と対策について解説しました。社内Wikiは、業務効率化や属人化の解消などさまざまなメリットのあるツールです。操作性の高いツールを導入し、ルールを明確にした上で積極的に活用されるように対策を立てましょう。
投稿や編集などにインセンティブを設ける、導入目的を明確にするといった対策が有効です。
継続的に活用される仕組みを整えることで、社内Wikiは組織全体の知識資産として大きな力を発揮します。まずは自社に合った運用ルールや活用方法を見直し、社内Wikiの定着を目指しましょう。