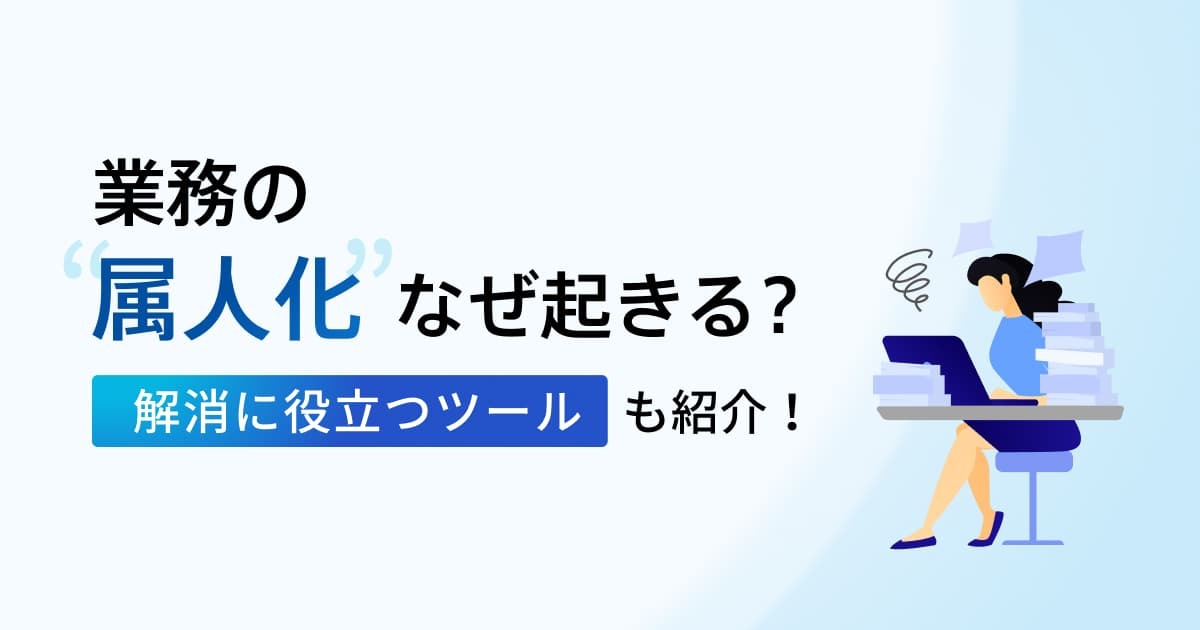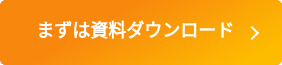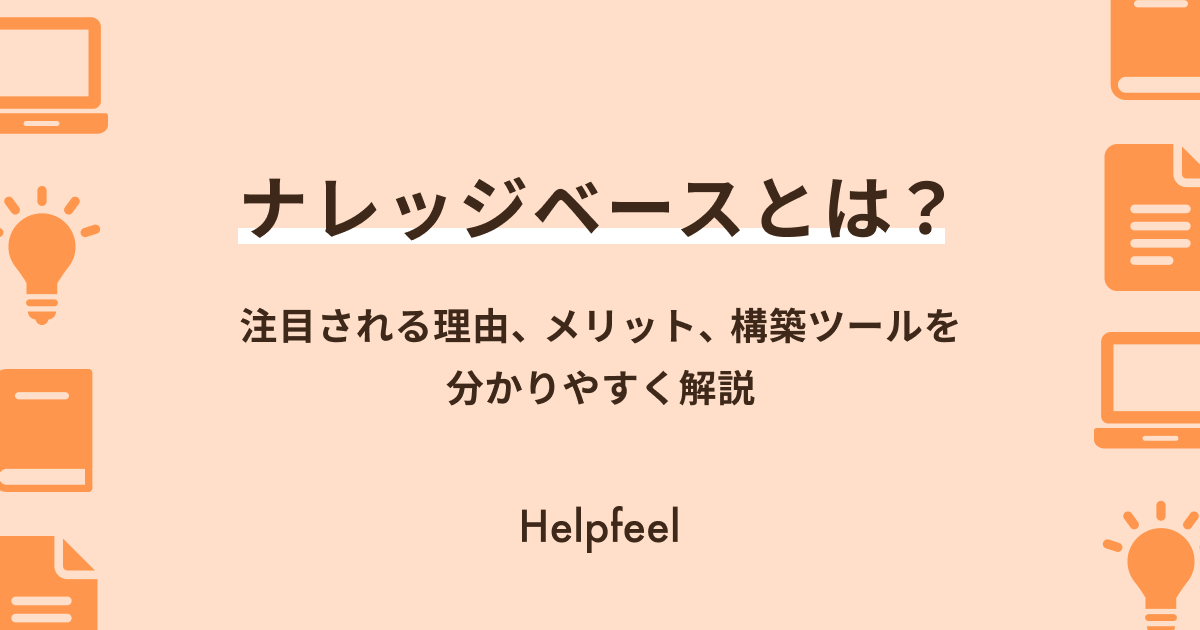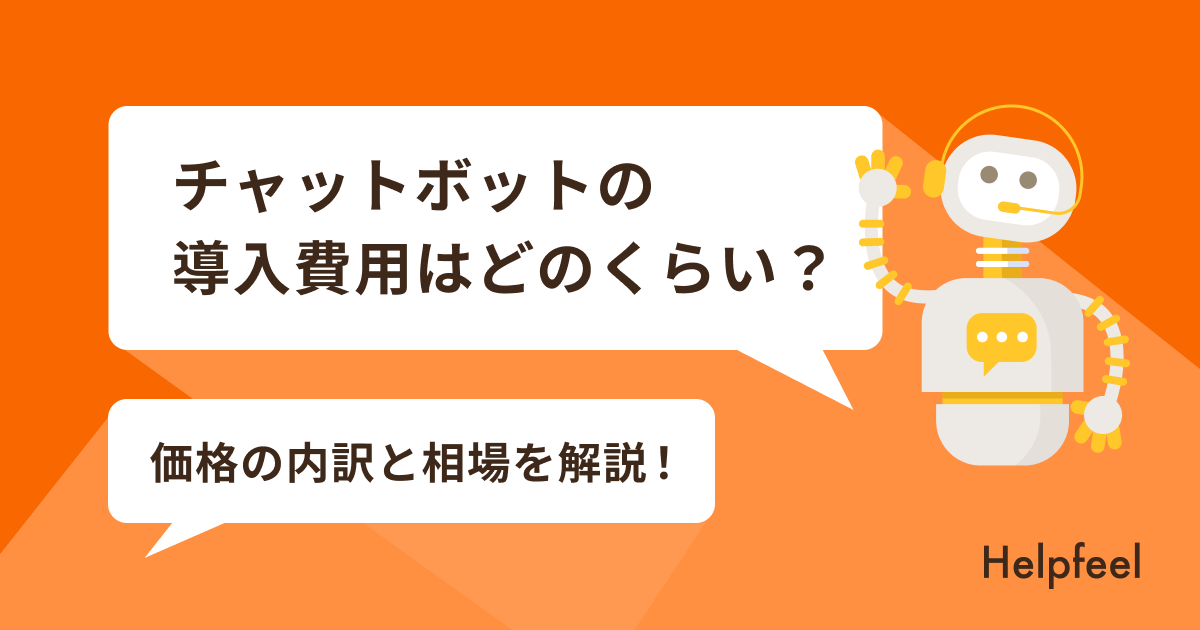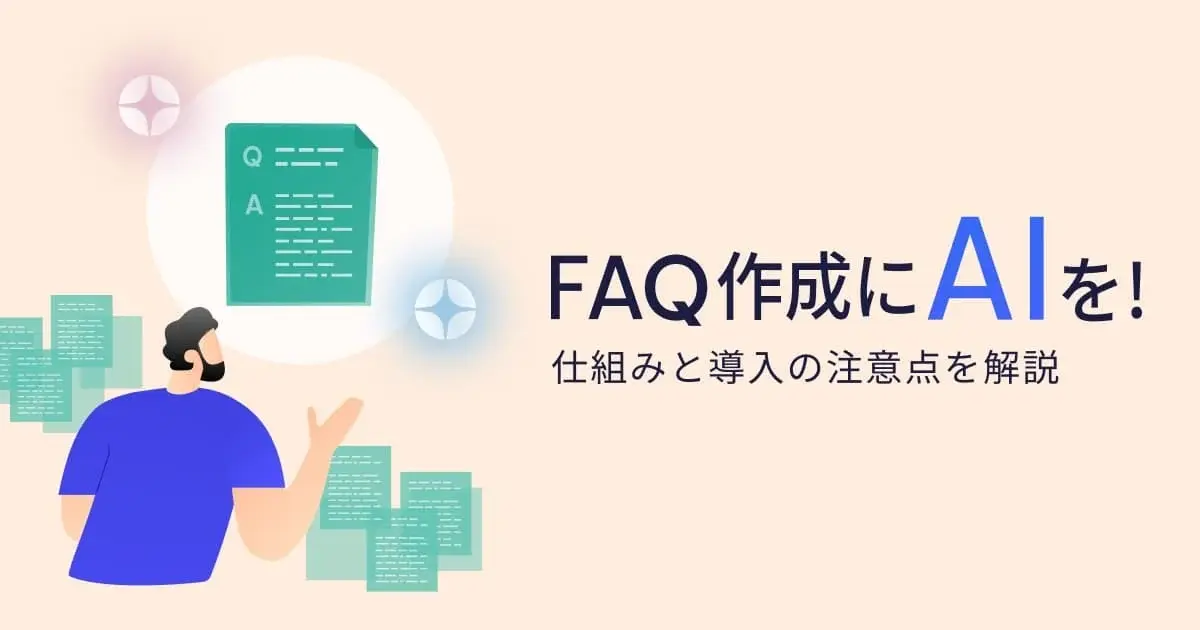ナレッジマネジメントとは

ナレッジマネジメントとは、個々が持っている業務に関する知識やノウハウ(=ナレッジ)を組織全体で共有して、業務効率化や生産性向上を図る手法です。
そもそもナレッジとは、マニュアルには載っていないちょっとしたコツや失敗から得た学び、トラブル時の対処法など、仕事を円滑に進めるための「経験にもとづく知識」全般を指します。
ナレッジマネジメントを効率的に進めるために使われるツールをナレッジマネジメントツールと呼び、ツールを利用することで業務効率化や生産性向上を実現できます。
▼あわせて読みたい
ナレッジマネジメントが重要視されている背景
ナレッジマネジメントの概念自体は1990年代からあるものの、近年は需要が高まってきています。その背景として、企業における人材の流動化が進んだことが影響していると考えられます。
これまでは終身雇用制度により、1つの企業に長く勤めるのが一般的でした。そのため、上司個人が持つスキルや知識を直接部下が学ぶことができていたのです。
しかし、近年は人材の流動化が進んだことで、個人が持つスキルや知識を共有するのが難しくなってしまいました。そのため、企業に個人のスキルや知識を共有し、ストックできるナレッジマネジメントの需要が高まったのです。
また、働き方改革によってさらなる生産性の向上に向けた取り組みが必要だったり、テレワークの普及から社員一人ひとりの知識・情報の格差が広がりを見せていたりすることも、ナレッジマネジメントの需要を高めている理由の1つとなっています。
ナレッジマネジメントツールを導入するメリット

ナレッジマネジメントツールを導入することで、主に以下のメリットが得られます。
|
それぞれのメリットについて詳しく解説していきましょう。
属人化の防止
業務知識や経験が全体共有されず個人のみで保有されたままだと、業務がブラックボックスとなり、属人化しがちです。一人の担当者のみが業務に関する知識を保有していた場合、その社員が異動したり退職したりすると業務に関する知識ごと失ってしまうおそれがあります。
業務の滞りと品質低下を防ぐためにも、ナレッジマネジメントツールを使って知識を蓄積し、担当者が変わってもこれまでと同じように対応できる環境を構築することが重要です。
▼あわせて読みたい
生産性の向上
ExcelやWordなどのツールを使ってナレッジを蓄積することも一般的ですが、手作業で情報を整理する必要があり、人数規模が増えたり、内容が複雑だとどうしてもメンテナンス工数が大きくかかります。
また、蓄積したナレッジの中から必要な情報を見つけ出せない、情報へたどり着くのに時間がかかるなど、ナレッジを活用する場面での不便さが生じるケースが少なくありません。
その点、ナレッジマネジメントツールを利用すれば手軽に情報を蓄積できるうえ、多くの情報の中から必要な情報をスムーズに検索できるため、業務の生産性向上が可能となります。
部門間の連携の強化
ナレッジマネジメントツールは部門間の連携を強化するのにも役立ちます。企業は基本縦割りの組織になりやすく、部門間における連携が希薄になってしまうことも少なくありません。
しかし、ツールを導入することにより各部門がそれぞれ保有していた知識・情報をツール上で共有でき、なおかつツールを通して部門間で連携を図ることも可能です。
たとえば開発部が蓄積したナレッジを、ツールを通じて営業部やカスタマーサポートなどに共有した場合、営業時の販促活動や顧客から問い合わせがあった際の対応などに活用することも可能です。逆にカスタマーサポートで得た顧客の声を開発部とも共有することで、新たな商品開発に活かせます。
さらに、部門間に限らず店舗間の連携強化にも役立ちます。1つの店舗で発生したトラブルを共有することで、他の店舗でそのトラブルに対する予防も可能になります。また、高評価を得ている店舗の顧客対応を共有することで、顧客対応の質を全店舗で底上げすることも可能です。
企業としての競争力の強化
業歴の長い社員が持つノウハウを、若手社員にも共有することにより、一人ひとりのスキルアップはもちろん、企業全体の底上げにもつながります。その結果、企業としての競争力も強化されるのです。
たとえば、ナレッジを企業全体に共有することで新たなアイデアが発掘され、商品・サービスの開発も加速する可能性があります。新たな商品・サービスの開発により、市場での競争優位を保つことも可能です。
人材育成での活用
ナレッジマネジメントツールの導入は、人材育成の効率化につながるというメリットがあります。たとえば、配置転換で社員が新しい業務に就く際、直接知識を伝えていると、教育に多くの工数が発生してしまいます。
ナレッジマネジメントツールを業務マニュアルとして活用すれば、社員が自ら検索して情報を得られるため、教育にかかる工数を削減できます。
▼Helpfeelの社内ナレッジシステムなら、すぐにナレッジを共有・蓄積ができ、組織の底上げをサポートします。
ナレッジマネジメントツールの種類

ナレッジマネジメントツールは、大きく分けて3つの種類があります。
1.FAQツール
FAQはよくある質問を蓄積できるツールで、社員がわからないことを検索すれば解決策に関する情報へとたどり着けます。そのため、社員の教育工数削減や業務の効率化におすすめです。
▼あわせて読みたい
2.社内wiki
社内wikiは業務に関する情報を社員が自ら書き込んでいく、社内専用のWikipediaのようなものです。
社員が書き込み・編集できるため、多くの情報や最新の情報を蓄積できます。業務に関する情報の一元管理や、スピーディーな情報更新をおこないたいシーンでおすすめです。
▼あわせて読みたい
3.社内SNS
社内SNSは主にコミュニケーションを目的としたツールですが、業務に関する情報共有にも利用できます。また、1対1のコミュニケーションが取れるため、社員同士のコミュニケーション促進や、部下のマネジメントにも利用できるなどのメリットもあります。
ナレッジマネジメントツール選定のポイント

実際にナレッジマネジメントツールを導入する場合、自社に適したものを選定する必要があります。ここでは、どのようなポイントを押さえて選定すべきかを5つご紹介しましょう。
1. 操作性や検索性は問題ないか
ナレッジマネジメントツールは社員一人ひとりが持つナレッジを共有するために、登録・活用できるようにする必要があります。これを実現するためには操作性や検索性が重要となってくるでしょう。
たとえばナレッジを登録する際の入力フォームがシンプルでわかりやすかったり、登録したナレッジを活用する際にどこにあるのか検索しやすかったりするなどです。
複雑な操作を必要とする場合や検索しにくい場合、徐々に活用しなくなる社員も増えてきてしまいます。マニュアルを読まなくても把握できるようなわかりやすい操作性と、タグ付けや複数の条件から検索できるなど、現場で使用するうえで問題はないか確認してみてください。
▼あわせて読みたい
2. 専門知識がなくても使いやすいか
社員全員が活用できるようにするためには、専門的な知識がなくても使えるツールを導入する必要があります。特にITツールに使い慣れていない人でも操作できるよう、直感的な操作を可能にするツールであれば、より使いやすさも向上します。
専門知識がなくても使いやすいかどうかは、実際に使ってみなければわからない部分も多いです。そのため、いきなりツールを導入するのではなく、無料トライアルなどを活用してみて、本当に使いやすいかを試す必要があるでしょう。
3. モバイルやタブレット端末でも使用可能か
営業で外出先にいる場合やテレワークで在宅勤務をしている場合でも、ナレッジを登録・活用できるようにするためには、PCだけでなくモバイル・タブレット端末でも使えるツールを選ぶことが大切です。
たとえば専用のアプリをダウンロードしておけば、いつでもナレッジの登録や共有されたものを確認できるようになります。
マルチデバイス対応で、ブラウザ操作からモバイル・タブレット端末でも使えるツールもあるため、使用する環境に合わせて選べると良いでしょう。
4. スモールスタートは可能か
ナレッジマネジメントツールは、導入してから間もない時期だとツール内に蓄積されている情報が限られてしまい、社内からの問い合わせ件数も減らない可能性が高いです。まずは全社ではなく限られた部署やメンバーでスモールスタートをおこなった方が、全社で取り入れる際にスムーズな運用が可能になるでしょう。
そのため、スモールスタートが可能かどうかもチェックしておきたいポイントです。利用規模や機能性を拡張できるツールだと、利用する人数が増えても安心して運用ができます。
5. セキュリティ対策はされているか
ナレッジマネジメントツールを選ぶ際に、セキュリティ対策も万全かどうかチェックすることが大切です。特にクラウド型のツールだと顧客情報を含むナレッジが蓄積されていくため、不正アクセスによる情報漏洩を防ぐ必要があります。
サーバーの監視体制やデータセンターが信頼できるかどうかなどを確認しておくと安心です。また、IP制限やIdP連携にも対応したツールだと、より安心して活用できます。
ナレッジマネジメントツール10選

現在リリースされているナレッジマネジメントツールにはさまざまな種類があり、それぞれで特徴が異なります。ここでおすすめのナレッジマネジメントツールを、厳選してご紹介します。
|
ツール名 |
特徴 |
|
Helpfeel |
独自技術「意図予測検索」機能により、検索ヒット率98%を実現。FAQの立ち上げから利用状況の分析・改善アクション提案など手厚い伴走体制が魅力。 |
|
COTOHA Chat & FAQ |
「意味検索エンジン」により高精度の回答を提供。利用を促進するサポートや利用状況の分析機能なども搭載。 |
|
Helpfeel Cosense |
業務マニュアルや簡単な情報共有が可能。専門的な知識を使わずに誰でもページを編集できる |
|
Notion |
ナレッジを共有するための社内wikiからメモ、タスク管理まで幅広い使い方が可能。日本語のチャットやテンプレート、ハウツー動画が豊富。 |
|
NotePM |
高機能エディタやテンプレート、画像編集機能を搭載。ファイルの中身まで検索できる機能も利用できる。 |
|
Talknote |
必要な情報を共有できるノートは投稿に対してコメントや「いいね」を送ることも可能。時系列で表示されるタイムラインで、リアルタイムにナレッジを共有できる。 |
|
esa |
何度も編集できる機能を使って情報のブラッシュアップが可能。タイトルに特定の記号を入れるだけでカテゴリ分けも簡単。 |
|
Evernote |
アクティビティの管理機能によって管理者が変更内容を確認できる。外部の主要ツールとも連携が可能。 |
|
flouu |
リアルタイムでの情報共有機能や見やすいナレッジを作成できる文書作成機能を搭載。ドラッグアンドドロップで簡単にファイルの添付もできる。 |
|
Knowledge Explorer |
AIの実装によって関連資料から今必要なナレッジを抽出できる。客観的な評価ができる機能やコメント機能も搭載。 |
※本記事の内容は、2025年12月時点の情報に基づいています。最新の仕様や価格については、公式サイトをご確認ください。
Helpfeel
- 製品サイト:https://www.helpfeel.com/
- 開発・提供元:株式会社Helpfeel
- 種類 :FAQ
- 機能・特長:
- 検索ヒット率98%を実現する独自技術「意図予測検索」が、ユーザーによって異なる検索語句を的確な回答へと導く
- 応答速度は従来の100倍となる0.01秒で、スピーディーな検索が可能
- FAQの立ち上げや既存コンテンツからの移行、利用状況の分析・改善アクションの提案など手厚い伴走体制が整っている
- 社内ナレッジの検索・活用にも強みを持ち、複雑なマニュアルや過去事例からも瞬時に最適な情報を引き出すことができる
- 価格:個別見積
- デモ・トライアル:無料デモあり
COTOHA Chat & FAQ
- 製品サイト:https://www.ntt.com/business/services/application/ai/cotoha-cf.html
- 開発・提供元:エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
- 種類 :FAQ
- 機能・特長:
- 独自の意味検索エンジンが質問の意図を読み取り、高い精度での回答を実現
- ドキュメントを読解し回答する自動回答や、Microsoft TeamsのUI上でチャットやFAQを利用できるオプションが豊富
- 精度向上や利用促進に向けたサポート、FAQの利用状況を分析する機能を搭載
- 価格:初期費用0円、月額料金104,500円(税込)〜
- デモ・トライアル:有料トライアル月額料金55,000円(税込)〜
Helpfeel Cosense
- 製品サイト:https://cosen.se/product
- 開発・提供元:株式会社Helpfeel
- 種類 :社内wiki系
- 機能・特長:
- シンプルな構成で、業務マニュアルから簡単な情報共有まで手軽に利用できる
- 専門的知識が不要で誰でも利用しやすく、リアルタイムで同時編集が可能
- 単語のリンクによってページを簡単に検索できるため、フォルダ構成や情報整理の必要がない
- 価格:
- PERSONAL / EDUCATION:無料
- BUSINESS:月額1,100円(税込)/ユーザー
- ENTERPRISE:サービスサイトに記載無
- デモ・トライアル:無料トライアルあり
Notion
- 製品サイト:https://www.notion.so/ja-jp
- 開発・提供元:Notion Labs Inc.
- 種類 :社内wiki系
- 機能・特長:
- メモやタスク管理、社内wikなどさまざまな使い方が可能
- パソコンやタブレット、スマートフォンなどさまざまな端末からアクセスして画像やテキストなど、あらゆる情報を集約できる
- EvernoteやTrelloなど他のツールからの移行が可能。日本語によるチャットやテンプレート、使い方に関する動画が豊富
- 価格:
- フリー:無料
- プラス:1,650円
- ビジネス:3,150円
- エンタープライズ:サービスサイトに記載無
- デモ・トライアル:無料トライアルあり
NotePM
- 製品サイト:https://notepm.jp/
- 開発・提供元:株式会社プロジェクト・モード
- 種類 :社内wiki系
- 機能・特長:
- 高機能エディタやテンプレート、画像編集機能で誰でも簡単にナレッジの蓄積やマニュアル作成が可能
- WordやExcel、PowerPointにPDFなどファイルの中身まで対象となる強力な検索機能が利用できる
- ページへアクセスしたユーザーの履歴や変更履歴の自動記録、レポート機能など情報共有の状況を把握できる機能もあり
- 価格:初期費用0円、月額4,800円(税込)〜
- デモ・トライアル:無料トライアルあり
Talknote
- 製品サイト:https://talknote.com/
- 開発・提供元:Talknote株式会社
- 種類 :社内SNS
- 機能・特長:
- 必要な情報を必要なユーザーに共有できるノートは、投稿へコメントやいいねが可能
- タスク機能には業務内容や期限が設定でき、期限を過ぎると通知でタスクの抜け漏れを防止
- タイムラインには時系列でノートが表示されるため、社内の情報をリアルタイムで効率良く収集できる
- 価格:
-
- 月契約月々払い:月額1,380円/ユーザー〜
- 年間契約一括払い:月額1,180円/ユーザー〜
- エンタープライズ:要問い合わせ
- デモ・トライアル:無料トライアルあり
esa
- 製品サイト:https://esa.io/
- 開発・提供元:合同会社esa
- 種類:社内wiki系
- 機能・特長:
- 社内の状況共有を円滑化してくれるツールで、何度も編集できる機能により情報をブラッシュアップしていくことができる
- 履歴管理機能が搭載されているため、万が一不適切な投稿をされた場合でも依然尾バージョンに戻せるようになっている
- 情報整理機能により記事タイトルに特定の記号を入れるだけで、記事を手軽にカテゴリ分けできる
- 価格:月額500円(税込)/ユーザー
- デモ・トライアル:無料トライアルあり
Evernote
- 製品サイト:https://evernote.com/ja-jp
- 開発・提供元:エバーノート株式会社
- 種類:社内wiki系
- 機能・特長:
- メモアプリとしても活用されているEvernoteは、ノートのようなシンプルな使い心地が魅力。社内wikiや議事録など、幅広い活用方法がある
- アクティビティの管理機能によって各アカウントがおこなった変更内容を管理者側でチェックできる
- Microsoft TeamsやGoogleドライブなど主要ツールとの連携も可能。Googleドライブとの連携により、直接ファイルをEvernoteに保存できる
- 「あいまい検索機能」や「PDFとファイル内検索」などの高度な検索機能も搭載
- 価格:
- FREE:無料
- PERSONAL:月額1,100円/ユーザー
- PROFESSIONAL:月額1,550円/ユーザー
- ENTERPRISE:要問い合わせ
- デモ・トライアル:無料トライアルあり
flouu
- 製品サイト:https://lp.flouu.work/
- 開発・提供元:プライズ株式会社
- 種類:社内wiki系
- 機能・特長:
- リアルタイムでの情報共有機能や、文字装飾・表による情報整理など、見やすいナレッジを構築できる文書作成機能を搭載
- ExcelやWord、PowerPoint、PDFファイル、画像・動画をドラッグアンドドロップで手軽に添付することもできる
- 階層構造でのナレッジ管理やラベル貼り付けによる情報整理が可能で、どこに必要なナレッジがあるかわかりやすい
- 価格:
- 基本料金:30日660円/ユーザー(1GB付与)
- セキュリティオプション:30日550円/ユーザー
- OCRオプション:30日220円/ユーザー
- デモ・トライアル:無料トライアルあり
Knowledge Explorer
- 製品サイト:https://www.presight.co.jp/product/knowledgeExplorer.php
- 開発・提供元:株式会社図研プリサイト
- 種類:情報収集系
- 機能・特長:
- AIの実装によりナレッジの抽出や同じテーマの文書検索がラクにおこなえる
- ナレッジを客観的な視点から評価する「評価・コメント」機能も搭載。他のユーザーからの評価が可視化されているため、ドキュメントの良し悪しを見る前に判断できる
- クラウドにデータをアップロードする必要がなく、すべて社内ネットワークで完結できる
- 価格:個別見積
- デモ・トライアル:トライアルあり(無料かどうかは不明)
ナレッジマネジメントツールの活用事例

ツールを導入したことにより、恩恵を受けた企業も少なくありません。そこで、実際にナレッジマネジメントツールを活用した事例をご紹介します。
パーソルテンプスタッフ株式会社
パーソルテンプスタッフ株式会社は人材派遣やアウトソーシング事業を手掛ける企業です。
顧客の持続的な事業成長を目的に、BPO事業企画室がサービスの企画推進業務をおこなっていますが、市場の拡大とともに組織やプロジェクトが拡大したことから、事業部全体での体系的なナレッジマネジメントを実施する必要がでてきました。
自由に検索してさまざまなページを回遊し芋づる式に関連情報をたどれるという理由で、ナレッジマネジメントツールとして「Helpfeel」を導入されました。
運用が軌道に乗ってからは、「今まで探せなかった情報が見つかる」といった声が増え始めました。ナレッジを投稿してくれた人にはポイント還元するという制度を導入し、「みんなで使い、育てる」という文化の醸成を目指しています。
▼事例詳細はこちら
ナレッジの蓄積や共有に課題を感じている、ナレッジマネジメントツールの導入を検討しているという方は、ぜひHelpfeelについてお気軽にお問い合せください。
ナレッジマネジメントツールを導入し、社内の情報共有の円滑化を図ろう

今回はナレッジマネジメントツールについてご紹介してきました。近年需要が高まっているナレッジの共有・活用は、ツールを取り入れることで効率化され、全社員のスキルの底上げが期待できます。自社に適したナレッジマネジメントツールを導入することで、より情報共有の円滑化につながるでしょう。
今回ご紹介したナレッジマネジメントツールなども比較しつつ、自社に適したツールを見つけてみてください。